
この記事は私の母が当時のことを思い出しながら執筆しました!
アメリカで子どもが現地校に通い始めたとき、胸の中にずっとあったのは「もし仲間外れや嫌なからかわれ方をしたらどうしよう」という不安でした。
私自身は大人として違いを面白がる余裕が多少あるのですが、子どもにとって新しい環境は“ゼロからの挑戦”。文化も言葉も異なる中で、友達を作れるのか、授業についていけるのか、親の心配は尽きませんでした。
本記事では、実際の体験や周囲の日本人家庭の話を交えながら、孤立やいじめの壁をどう乗り越えたかを具体的にお伝えします。
最初に起きた“無視”という壁

入学して最初の1週間、我が子がポツリと「誰も話しかけてくれない」と言ったとき、胸が締めつけられる思いがしました。
言葉が通じないからか、授業中に話しかけられることもなく、ランチタイムもひとりで座っていたそうです。いじめというより「興味を持たれない」という距離感が、本人には“拒絶”のように感じたようでした。
先生への相談のタイミングと伝え方
数日悩んだ末、担任の先生に勇気を出して英語でメールを書きました。「My daughter is having a tough time making friends.」と、直接“bullying”という言葉を避けつつも、今の心境を伝えました
すると先生はすぐに返事をくれ、翌週から“Buddy”役を決め、授業中や休み時間に一緒にいてくれる子をつけてくれました。その変化は子どもの表情にすぐ現れ、私も少しだけ肩の荷が下りた気がしました。
アメリカの“いじめ”の定義と対応システム

アメリカでは“Bullying”に対して学校側も社会も非常に厳しい姿勢を取ります。繰り返される悪意のある攻撃と定義され、起きた場合にはカウンセラー面談、当事者と保護者の話し合い、再発防止プランなどがすぐに動き出します。
実際、日本人家庭の友人の息子さんは「目が細い」とからかわれたとき、すぐ学校に相談。数日以内に先生・加害児童・保護者・カウンセラーとの一連の対応が行われ、学校側がしっかり「守る姿勢」を見せてくれました。その素早さは、日本との大きな違いを感じさせました。
- 明確な定義がある(繰り返される、意図的な攻撃など)
- いじめが発覚した場合の対応マニュアルがある
- スクールカウンセラーや心理士が常駐している学校も多い
カウンセラー制度の活用

アメリカの公立校で特徴的だったのは、子どもの心のケアに専門スタッフが必ず配置されていることでした。
私の子どももある日、担任に勧められてスクールカウンセラーと一度面談。“ここでは何を話してもいいんだよ”と優しく言われたそうで、帰宅後に「ちょっと安心した」と笑顔を見せてくれました。
日本では保健室や先生が対応することが多いですが、現地校では「心の専門家」にいつでもアクセスできる点が大きな安心材料でした。
“軽いいじり”にどう対処するか
我が子は日本から持たせたおにぎりをランチに食べていましたが、ある日「It looks weird!」とクラスの子に笑われて深く落ち込みました。
ところが次の日、「Can I try one?」と声をかけてくれた子がいて、おにぎりを一緒に食べることに。
その瞬間、子どもの表情がパッと明るくなったのを覚えています。さらに先生が“Cultural Show & Tell”という活動の一環で日本のお弁当文化を紹介する場を設けてくれ、笑われた存在が一転して注目と尊重の対象となりました。
この経験は子どもに「自分の文化を誇っていい」という自信を与えてくれました。

こうしたサポートはお互いの文化理解のためにもありがたいですよね!
親ができる心構えとサポート

子どもとの対話を欠かさない
毎日の「今日どうだった?」という会話が、早期発見につながります。
小さなサインを見逃さない
我々親にできるのは、毎日の小さな会話を欠かさないことです。「今日は誰と一緒にいた?」「お昼は楽しかった?」と聞くだけでも、子どもの心は少し和らぎます。
さらに、元気がなくなる・目を合わせなくなるといった小さな変化のサインを逃さないことが重要です。問題が起きたら学校と対立するのではなく「どう協力できるか」という姿勢を見せることで、先生方も気持ちよく動いてくれます。
そして家では日本語で思いを解放できる環境をつくり、安心できる居場所を与えることが、何よりも大切だと思いました。向けましょう。
学校と“味方として”協力する
問題が起きたとき、「攻める」のではなく「協力したい」という姿勢を伝えることで、先生側も前向きに対応してくれます。
日本語で安心を提供する
家では安心して話せる環境をつくり、言葉のストレスから少しでも解放してあげることも大切です。
最後に:海外だからこそ“見守る力”が問われる
異文化の中で子どもが傷ついたとき、親としてはすぐに守ってあげたい気持ちになります。
でも、アメリカの学校には子どもが自分で声をあげるための支援体制が整っているのも事実。
私たち親にできるのは、
- 子どもが困ったときに相談できるように信頼関係をつくること
- 学校と協力して“居場所づくり”をすること
- 過保護になりすぎず、でも放置しない“中間の距離”をとること
文化も言葉も違う環境での子育ては、不安と勇気の連続です。
でも、一つひとつの壁を乗り越えるたびに、親も子も、きっと強くなれる。
この記事が、今まさに同じような不安を抱えている方の支えになれば幸いです。
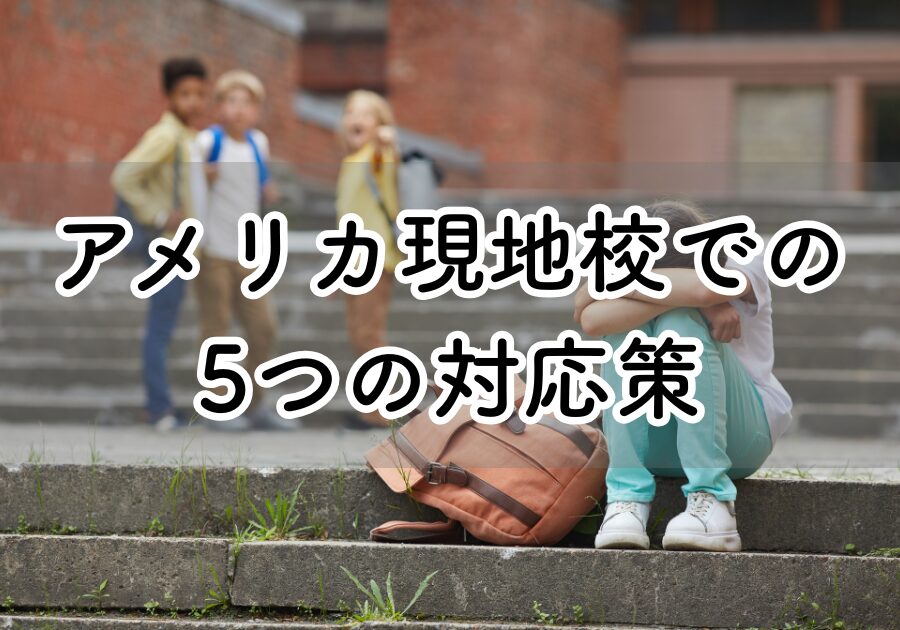
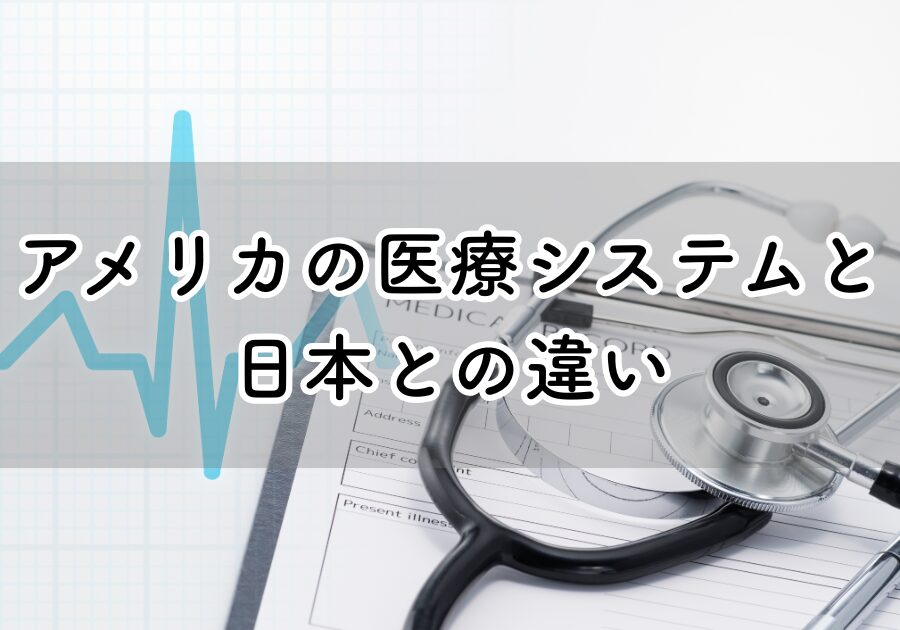
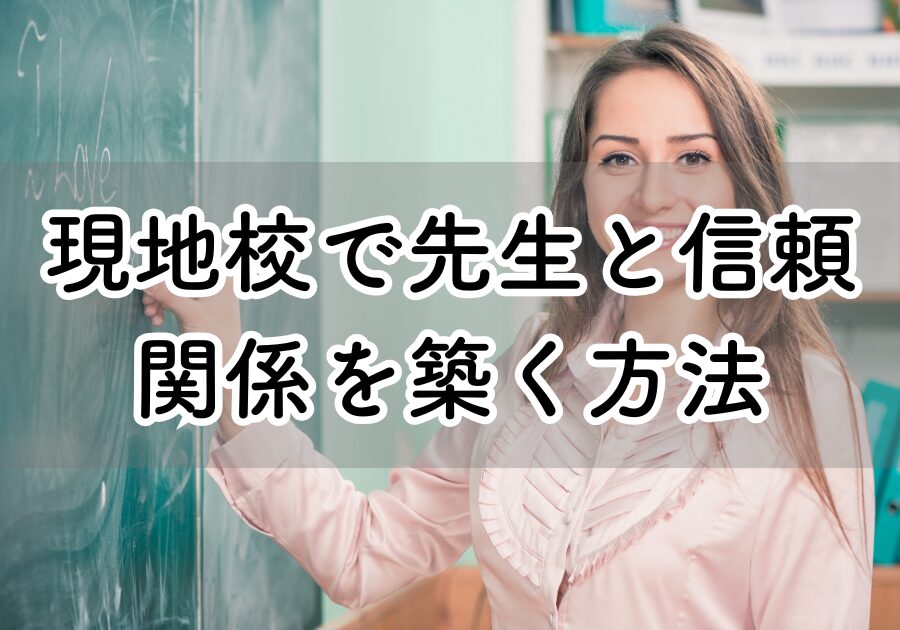
コメント