中学・高校時代をアメリカで過ごした私は、現地での生活の中で「ボランティア活動」に触れる機会に恵まれました。
当時はまだ英語も不慣れで、文化の違いに戸惑う日々を送っていましたが、ボランティアを通じて、学校では得られなかった経験や人とのつながり、そして自分自身の成長を感じることができました。

この記事では、学生時代の私が参加したボランティア活動と、そこで得た学びについてお話ししたいと思います!
図書室ボランティアで初めて感じた「居場所」

私がアメリカの学校で最初に経験したボランティアは、図書室でのサポート活動でした。
当時、母が学校のPTA活動に関わっていて、ある日「一緒に何か手伝ってみない?」と誘いを受けたのです。
現地の生活はまだ始まったばかりで、英語での日常会話は何とかこなせるものの、自分の伝えたいことがうまく伝わらないことに大きな不安を感じていました。
初めて図書室のドアを開けた瞬間、知らない環境に背筋が凍るような緊張を覚え、手がふるえていたのを今でもはっきり思い出します。にもかかわらず、数人の先生方やスタッフが温かい笑顔で迎えてくれたことが、何よりも救いになりました。
それはまるで「ここにいていいんだよ」と言われたようで、私の心の壁をじわじわと溶かしてくれたのです。

英語が完璧でなくても、自分の存在を歓迎してもらえたことが嬉しくて、「自分にもできることがある」と思えた最初の経験でした。
イベント準備で学んだ、“積極性”の大切さ

図書室での活動を続ける中で、だんだんと顔を覚えてもらえるようになり、ある日、「今度のフリーマーケットの準備も手伝ってくれない?」と声をかけていただきました。
放課後、体育館に集まって、机やイスの配置を決めたり、飾り付けをしたりと、準備作業は意外と本格的で、英語での指示を聞きながら行動するのは簡単ではありませんでした。最初は指示が聞き取れずに戸惑うことも多く、周りのテンポについていけずに焦る場面もありました。
しかし、途中で他のボランティアの生徒が「わからなかったら一緒にやろう」と手を差し伸べてくれて、その一言にとても救われました。英語力よりも「やってみよう」という姿勢が評価されること、そして、完璧でなくても積極的に動くことが大切だということに気づかされました。
私が学んだのは、「たとえ失敗しても、まずは自分から動く勇気が大切だ」ということでした。初めてのイベント準備の際、英語の指示がどうしても聞き取れず戸惑うこともありましたが、周囲の温かいサポートで何とか乗り越えました。
あのとき、完璧に話せなくても、真摯に挑戦し続ける姿勢が人を動かすのだと体感しました。そんな経験が、私の自己肯定感の基盤となり、今でも新しいことに挑戦するときの支えになっています。

「失敗してもいいから、とにかく一歩踏み出してみる」。そんな当たり前のことが、自分の中で少しずつ身についていった気がします
地域図書館での読み聞かせ——自分のルーツと向き合った日
もうひとつ、特に印象に残っているのが、地域の公共図書館で行われた「多文化読み聞かせイベント」です。
「日本語の絵本を紹介してみない?」という案内があり、現地のライブラリアンから直接声をかけていただいたことがきっかけでした。
私は、日本語と英語の両方で絵本を読み聞かせする役を担当しました。事前に何度も発音を練習し、どこで声に抑揚をつけるか、どの場面でページをめくるかなど、細かいところまで練習しました。英語のセリフを読むときには、普段よりも大きな声で話さなければ聞き取ってもらえないということにも気づき、自分の“伝える力”と向き合う時間にもなりました。
イベント当日は、日系やアジア系の家庭のほか、アメリカ人の親子もたくさん集まりました。「日本語ってどんな響きなの?」と興味津々な子どもたちの目がとても印象的でした。
イベント後、一人の母親が私のところに来て、「子どもが日本語で『こんにちは』と言えるようになりました」と嬉しそうに話してくれたことが今も忘れられません。
言葉を超えて、文化や気持ちが伝わる瞬間に立ち会えた喜びが、私の心に深く刻まれました。自分のルーツを紹介することは、多様な価値観を尊重し合う架け橋になる。そんな実感を得たのは、この時が初めてだったのです。

自分が育ってきた文化を伝えることが、誰かの新しい知識や好奇心につながる。その喜びを初めて実感した体験でした。
食品配布センターで触れた、“支え合う社会”の姿

高校生になってからは、地域のフードバンク(食品配布センター)でのボランティア活動にも参加しました。
ここでは、月に数回、経済的に厳しい家庭や高齢者の方々に向けて、無料で食材を配布する取り組みが行われていました。
私の担当は、配布用の食品を箱詰めしたり、受付で名前をチェックしたり、荷物の運搬をサポートすること。活動はかなり体力を使いましたが、終わったあとの疲労感よりも「今日も誰かの役に立てた」という充実感のほうが大きかったのを覚えています。
特に印象的だったのは、受け取った方々が「Thank you so much」と心から感謝の気持ちを伝えてくださったことです。
日本にいた頃は困っている人に支援を受けることに少し遠慮がありましたが、アメリカでのフードバンクでの活動は私の価値観を大きく変えました。
ここでは「助け合い」が当たり前の日常で、支援を受けることも、支えることも、互いに尊重し合う社会の一部として自然なことなのです。誰かのために荷物を運びながら、多様な人々の笑顔に触れるうちに、人とのつながりが目に見えない大切な絆として私の心に根づきました。
ボランティア活動がもたらした“心の変化”
アメリカでボランティア活動に参加する前の私は、「英語もできないし、知らない土地で何ができるんだろう」と自信がありませんでした。
けれど、実際に一歩踏み出してみると、“役に立ちたい”という思いに国境や語学の壁はないのだと気づかされました。
むしろ、ボランティア活動は「失敗しても大丈夫な場」であり、「お互いさま精神」が根付いている場所。そこでの出会いや経験は、アメリカ生活をより豊かに、そして前向きにしてくれる大きな力になりました。
親子で参加した清掃活動——“小さな行動”の積み重ね

あるとき、近くの公園で行われた清掃活動にも、家族と一緒に参加しました。
地域の小学校が主催しており、「親子で参加できる」ということもあり、軽い気持ちで申し込みました。
ゴミ袋と軍手を手に、公園内を歩きながらゴミを拾ったり、落ち葉を掃いたり、ベンチを拭いたりと、作業自体は地味でしたが、活動が終わる頃には、公園がまるで生まれ変わったように見えたのが不思議でした。
終わったあとに、母と「なんだか気持ちがすっきりしたね」と話しながら帰ったあの感覚は、今でも忘れられません。

自分の手で誰かの役に立てたという実感、小さな行動の積み重ねが地域を良くするという実感は、ボランティア活動の中でもとても大きな学びのひとつでした。
まとめ:誰かのための行動が、自分自身を育ててくれる

私のアメリカでのボランティア経験は、「誰かのために何かをする」ことが結局は自分自身の成長と自信につながることを教えてくれました。
語学への不安を超えて挑戦したあの日々は、異文化の中での孤独感や戸惑いをやわらげ、私の人生に新しい価値観と希望をもたらしてくれました。
この記事を読んで、少しでも「自分も頑張ってみたい」と感じた方がいたら、ぜひ一歩踏み出してみてください。どんなに小さな行動でも、やがてそれがあなたの未来を豊かにする大きな糧となるはずです。
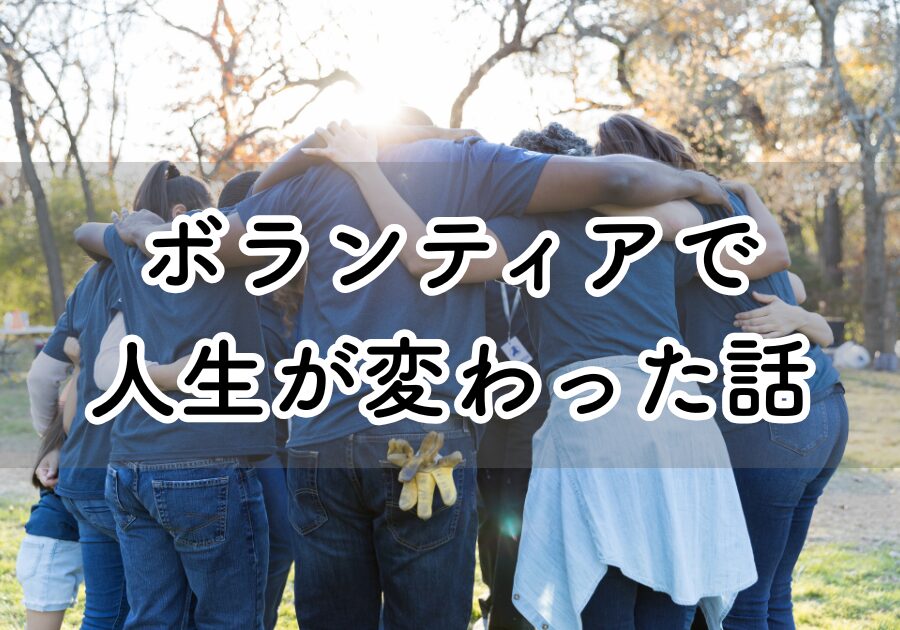

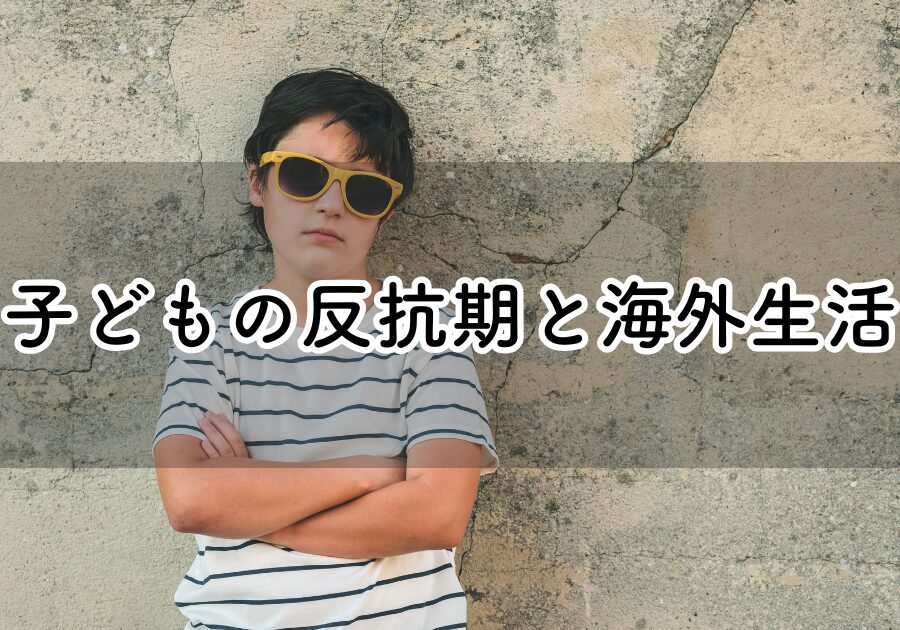
コメント