アメリカでの生活が始まったばかりの頃、私は13歳でした。
引っ越し先の見慣れない街も、初めて入る学校も、右も左もわからない日々。目に映るものすべてが新鮮である一方で、それと同じくらい、自分の居場所がどこにもないような心細さを感じていました。
学校の授業についていくのも精一杯で、放課後はどっと疲れて家に戻るだけの毎日。何かを始めようという気持ちになるには、もう少し時間が必要だったと思います。
でも、あの頃の私を少しずつ変えていったのが、アメリカならではの“課外活動”でした。

今振り返れば、あの経験が、「私は何が好きか」「どんなことで心が動くのか」を初めて知るきっかけだった気がします。
放課後にクラブがない?時間の概念がまるで違った

まず驚いたのは、課外活動の“時間割”でした。
日本では、学校のクラブ活動といえば「放課後」。制服のまま体育館や音楽室に移動して、そのまま練習や作業に入るのが当たり前でした。
ところがアメリカでは、そうではありません。
チェスクラブは朝7時から、ドラマクラブは土曜日の午後。あるクラブは授業の一部として行われるし、またある活動は学校とはまったく別の場所、週末の地域センターで開催されていたりします。
最初はただ戸惑いました。「なぜこんなにバラバラなんだろう?」と。
でもあとになって気づいたのは、これは「一律に何かを与える」という発想ではなく、「それぞれの子どもが自分に合う形で参加できるようにする」という考え方なのだということ。

自由で柔軟。でも、慣れていない私たちにとっては、予定を組むだけでひと苦労でした。
「STEM Girls」との出会い──苦手の中に芽生えた好奇心

そんなある日、学校の掲示板に貼られていた一枚のチラシが、ふと私の目にとまりました。
“STEM Girls Club – Hands-on Science for Curious Girls!”
(STEM女子クラブ──科学が好きな女の子たち、集まれ!)
STEMという言葉は、授業の中で何度か耳にした程度。
正直、理科はずっと苦手でした。教科書を読むだけでも頭が痛くなるし、数字の多い問題は途中で放り出してしまいたくなる。でも、その日はなぜか引き寄せられるように、その紙をじっと眺めていたんです。
「実験なら、少しは面白いかもしれない」
そんな思いを胸に、私は母に参加の相談をしました。
当日、現地の大学の理工系キャンパスに足を踏み入れた瞬間のことは、今でも鮮明に覚えています。
高い天井、光が反射するガラス張りの廊下、白衣をまとった大学生たちの笑顔。どれも、まるで映画のセットの中にいるような感覚でした。
その日の実験は「炎色反応」。
薬品を混ぜた金属片を火にかざすと、炎の色が変化するというものでした。私の担当は銅。アルコールランプの先に火が灯り、ゆらゆらと立ち上る炎が、次第に深く美しい青緑色に染まっていく。
その瞬間、言葉にならない驚きと感動がこみ上げてきました。
「科学って、こんなに美しいんだ」
それまで教科書の中だけにあった“理科”という世界が、急に現実味を帯びて、すぐ目の前で息づき始めた気がしました。
「自分で選ぶ」ことの自由と責任──アートクラスで学んだ“表現”

少し経ってから、地域のアートクラスにも通うようになりました。
学校とは無関係の活動で、場所は地元のコミュニティセンター。そこでは、小さな子どもから高校生まで、年齢も背景もバラバラの子どもたちが、それぞれの作品に向き合っていました。
初日に先生から言われたのは、「今日のテーマは“今の気持ち”よ。何を描いてもかまわない」という一言だけ。
驚きました。
日本の美術の授業では、題材も構図も「こう描きましょう」と決められていたので、“自由に描いていい”と言われても、何をどうしていいのかわからなかったのです。
キャンバスを前にしばらく悩んだ末、私は当時の自分の心の中をそのまま描くことにしました。スマホの画面に浮かぶLINEの通知、日本に残してきた友人のアイコン、桜の花びらが舞うような背景。
誰かに見せることを前提にしていなかったぶん、正直で少し切ない作品ができあがりました。
それを見た先生が、そっと肩に手を置いて、「これはあなたにしか描けない絵ね」と言ってくれたんです。
“上手いかどうか”ではなく、“自分の気持ちをどう表現するか”が大切にされる場所。

それは、これまで経験したことのない創作の在り方でした。
“遊び”じゃない。その熱量と責任感に触れて

見た目には「自由で楽しい」アメリカの習い事ですが、その実態は決して“遊び半分”ではありません。
たとえば、私が一時期所属していた女子サッカーチームは、週に2回のトレーニングに加えて、週末は試合が組まれ、遠征も頻繁にありました。
6時集合で郊外のグラウンドへ移動。チームでの戦術ミーティングやストレッチまできちんと行い、試合後には反省会まで。
コーチたちの指導も熱心で、フィジカルだけでなく精神面も鍛えられる内容でした。
それだけではありません。親の関与も想像以上に求められました。
試合当日のスナック当番、応援グッズの制作、チームのイベントの運営…。
最初は戸惑っていた両親も、徐々に他の保護者と打ち解け、試合を一緒に観戦しながら笑い合うようになっていました。
アメリカの課外活動は、「家族も一緒に楽しむ文化」に支えられているのだと実感しました。
シーズンごとに変わる習い事。変わる自分。
アメリカの多くの習い事は「通年」ではなく「季節ごと」の申込み制。
春は演劇、夏はキャンプ、秋はロボティクス、冬はインドアスポーツ…。1年でまったく違う体験が次々とやってきます。
毎シーズン、申込サイトとにらめっこして、必要書類を提出し、タイムスケジュールを組む。
最初のうちは、正直かなり大変でした。特にサマーキャンプの申し込みは人気が高く、受付開始と同時に満席になることも。
でも、その手間の先には、毎回まったく新しい世界が待っていました。
「一度始めたら1年は続けなきゃ」という日本の習い事とは違って、「興味があるうちにやってみる」という軽やかさが、当時の私にはありがたかったのです。
まとめ:柔軟な姿勢で楽しむのがカギ
いま大人になって振り返ると、アメリカで経験した習い事の数々は、どれも単なるスキル習得の場ではなかったように思います。
それは、自分が「何に惹かれるのか」「どんなときに心が動くのか」を探る、小さな旅のような時間でした。
失敗してもいい。途中でやめてもいい。だけど、自分の意思で始めて、自分で考えて、動いてみる。その積み重ねが、少しずつ私に「自信」のようなものをくれた気がします。
アメリカの習い事は、決して“遊び”ではない。
でも、“義務”でもない。
その中間にある、“夢中になれるもの”との出会いが、確かにそこにはありました。
これからアメリカで暮らす方や、現地の課外活動に不安を感じている誰かに、少しでもこの経験が届けば嬉しいです。

迷っているなら、まずは一歩だけ。あなたの中の“好き”が動き出すかもしれません。


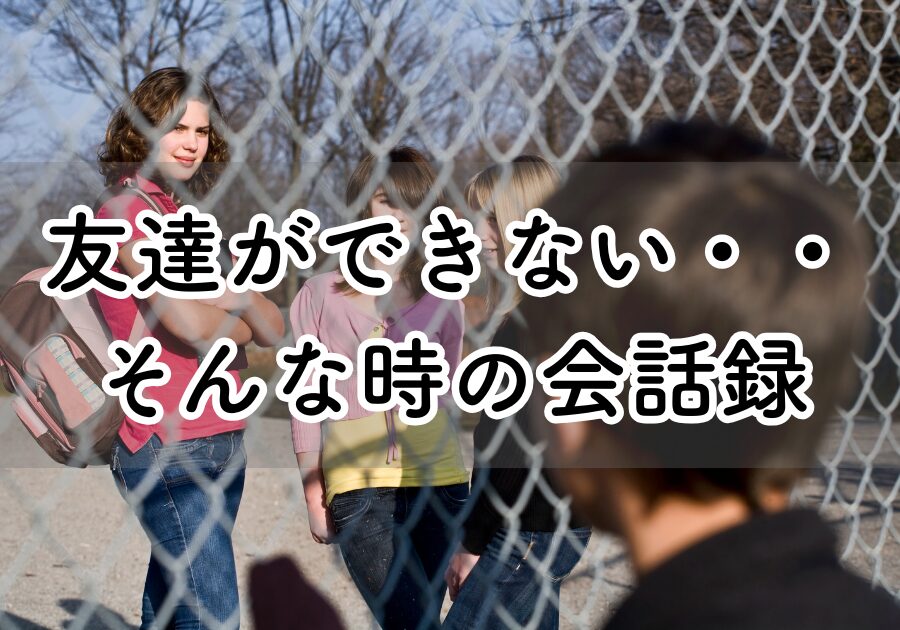
コメント