
この記事は私の母に当時を振り返って執筆してもらいました!
アメリカの学校に通い始めて、本当に驚いたことの一つが成績評価の仕組みです。日本のように点数の順位や偏差値で評価されるのかと思っていたら、「子どもたちの学びの姿勢」や「授業での関わり方」が重視されるまったく別物でした。
戸惑いながらも、一つ一つの評価内容に向き合い、親子で成長を感じながら過ごした日々はかけがえのない経験になっています。この記事では、我が家の子どもたち(小3・中1)の具体的な通知表内容と、親目線でどうサポートしてきたかを包み隠さずお伝えします。
アメリカの成績評価の特徴とは?
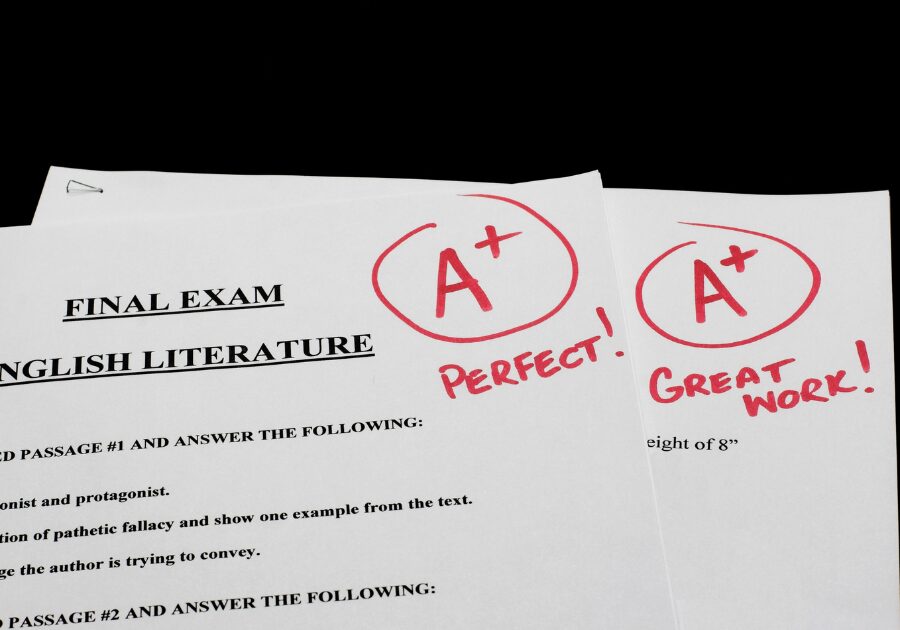
点数より“プロセス”重視
アメリカ現地校の通知表は、テストだけでなく「授業でどんなふうに取り組んだか」「友達と協力できたか」「自分なりに工夫したか」といった姿勢面が重視されます。
子ども自身の努力やチャレンジする姿、時には友達を助けたエピソードなど、“数字で現れない部分”がしっかり評価欄や先生のコメントに残るのが特徴的です。初めは分かりづらさも感じましたが、子どもと一緒に評価表を読み込むうちに、「今できること」よりも「これから伸びる力」が大切にされているのだと実感しました。
たとえば、次のような観点が通知表に含まれていました
- Academic Performance(学力):教科ごとの達成度
- Participation(参加姿勢):授業中の積極性や協働の様子
- Behavior(行動面):ルールを守れるか、周囲との関係構築
とにかくテストが得意で点数は良かったのですが、最初の通知表ではParticipation(授業参加度)が意外に低評価。
先生から「いつも静かにしているけど、発言もしよう」とコメントをもらい、本人も驚いていました。その後、勇気を振り絞って手を挙げたり、友達と意見交換する姿が増え、2学期には「チームワークが素晴らしい」と記述されるように。点を取るだけでなく「どうやって学ぶか」「どう関わるか」も学校生活の大事な一部だと気づかされました。
レターや記号での表記が多い
アメリカの通知表は、学校によって「A~F」や「E, G, S, N」などの記号や数字が使われています。たとえば小3の娘の成績表には、「Reading: G(Good)」「Writing: S(Satisfactory)」などが並び、その隣に必ず先生のコメント欄がありました。
コメントには「グループ活動で自分の意見を発表していたね」「新しいことに挑戦しようとする姿勢が見られた」といった具体的な場面がびっしり。点数以上に普段の子どものがんばりやクラスでの存在感が伝わるのが印象的でした。
中学校になると A〜F のレターグレードが一般的で、
- A:90〜100点
- B:80〜89点
- C:70〜79点
- D:60〜69点
- F:60点未満(不合格)
といった基準があります。加えて、“+”や“−”が付くこともあります(例:B+)。
成績表(Report Card)の中身とは?
学期ごとに配布される「Report Card」には、成績に加えて先生のコメントが必ず記載されていました。
小3の娘の例:
Reading:G(Good)
Math:E(Excellent)
Science:G
Writing:S(Satisfactory)
Behavior:G
先生コメント:"She is always kind to others and makes good effort. I encourage her to speak more during group activities."
「グループ活動でもう少し発言を」といったフィードバックがあり、“未来へのアドバイス”として機能している印象です。

アメリカでは特に主体的に授業に参加することが求められます。英語がまだできない頃は、それが心理的にも負担でした
成績の伝え方と保護者面談(Parent-Teacher Conference)

通知表を受け取ると、その内容について担任と直接話す保護者面談が開かれます。子どもも同席する場合が多く、先生と一緒に自作品やワークシートを眺めながら「どんな風に成長したか」「次は何を目標にするか」を確認するのが恒例です。
我が家の面談では、子どもが自信たっぷりに自作のポスターを見せながら先生と話し合う場面があり、普段の家庭では見えない子どもの成長ぶりに感動しました。親もしっかり意見を聞き、学校と家庭が二人三脚でサポートできる仕組みだと感じます。
- 学期ごとに面談(15〜20分程度)
- 担任と1対1で話す場で、子どもの様子を写真や作品とともに説明
- 子どもが同席することも(Student-Led Conference)
我が家の場合、娘が自分の作品を説明しながら「ここは先生に褒められた」と話す姿に驚きました。自分で自分の成長を把握する機会になっていると感じました。
宿題・課題の評価基準とは?
宿題は必ずしも毎日ではなく、週ごとにまとめて出るケースが多いですが、
- 提出期限を守る
- 自分の考えが入っているか
- 工夫やチャレンジが見られるか
といった“取り組む姿勢”が重視される傾向があります。
娘が「歴史上の人物について調べてレポートを書く」課題で、教科書を丸写しして提出したところ、「これはあなた自身の言葉じゃないね」とコメントされ減点。
→ 翌週、彼女は自分の言葉で書き直し、今度は「Great improvement!」のコメントをもらいました。
成績評価に対する親のサポート

「点数」で評価しない
成績が数字で出ない分、「今日はこんなことに挑戦できたね」「友達に自分の考えを伝えたのはすごいことだよ」など、努力や変化を具体的に認めて声をかける回数が増えました。
夕食時や寝る前には必ず「今日どんなことに挑戦した?」と問いかけ、一緒に小さな変化を積み重ねるのがアメリカ生活の日課になっています。
家庭でも、挑戦を肯定的に受け止め「やってみて良かったね」と声に出すことで、子ども自身も自信を持つようになったと感じます。
目に見えない成長を認める
たとえば:
- クラスで1回でも手を挙げたら「よく勇気出したね」
- 宿題に自分の考えを書いたら「いい視点だね」とフィードバック
「完璧さ」よりも「変化」や「挑戦」を家庭でも肯定することで、子どもは安心して取り組めるようになると感じました。
面談の内容を家庭でも共有
先生との面談や成績表に書かれていたコメントは、なるべく家族で共有するようにしています。「先生はこんなことを褒めてくれたよ」「次はこんなことをしてみたら?」と親子で話し合う時間を作り、子どもも自分の成長を意識できるようになりました。
課題点があるときも叱るのではなく、「じゃあ次はどうしてみる?」と一緒に作戦会議を開くことで、家庭と学校が協力して子どもを支えている実感があります。
英語が不安な親でもできること
英語が苦手でも、翻訳アプリや事前に質問したい内容をメモして面談に持参するなど工夫をしています。
実際に、重要な単語やコメントを家で一緒に調べて、家族全員の理解度をアップ。その結果、「英語が分からないから評価が分からない…」という不安が確実に減りました。
分からないことや質問が出た時には、遠慮せず先生や学校に相談しやすい雰囲気があるのも現地校の良さです。
まとめ:成績は“点”ではなく“線”で見る
アメリカの成績評価は、「今できること」よりも「これから伸びる力」に焦点を当てています。
親としてできるサポートは、
- 点数だけを気にせず、日々の成長を認めること
- 学校との対話を通じて子どもに合った声かけをすること
評価があるからこそ、子どもが“自分を振り返る機会”になります。日本とは異なるこのスタイルを楽しみながら、親子で“学びのかたち”を一緒に築いていくことが大切だと実感しています。
これから現地校に通わせる予定のご家庭に、少しでも参考になれば幸いです。
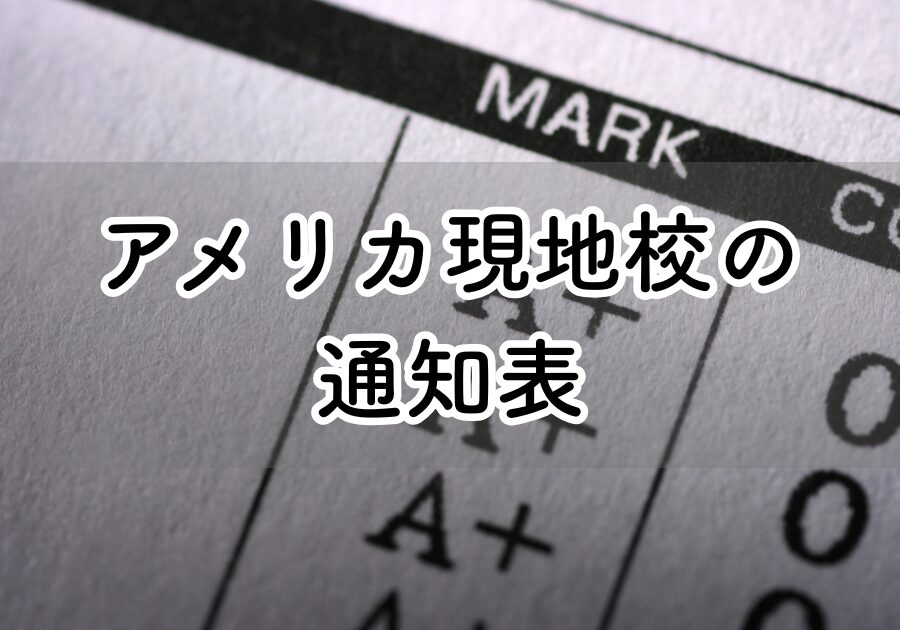
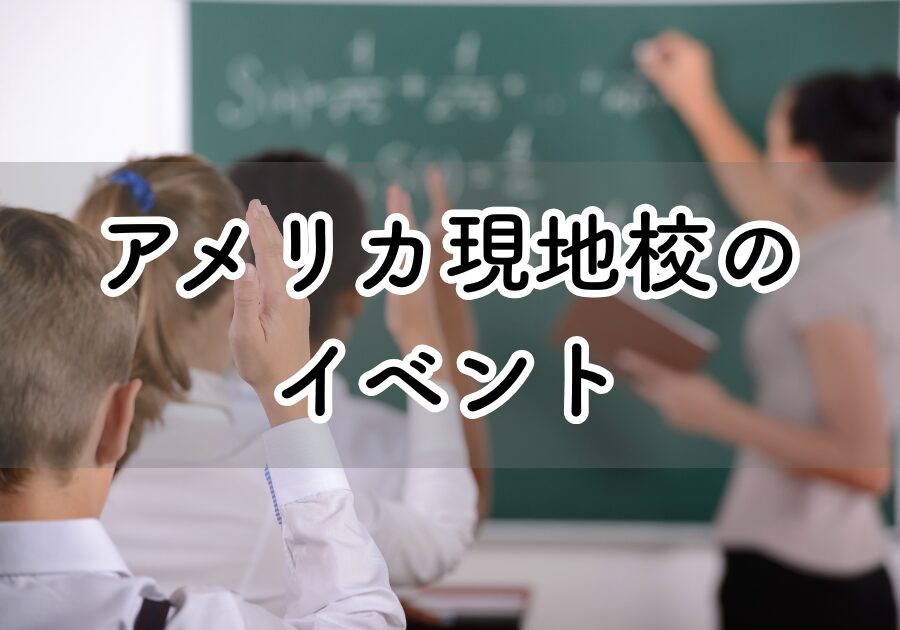
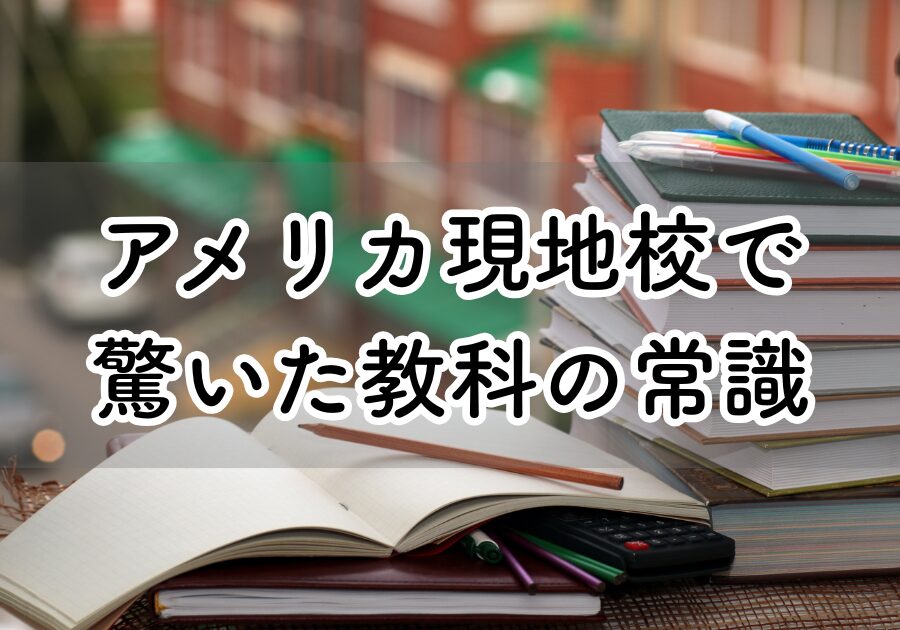
コメント