海外移住や長期滞在の準備で、多くの人がつまずくのが「ビザ取得」「保険加入」「各種書類手続き」です。
この一連のプロセスは、国によって制度も書式もバラバラ。日本の常識が通じないことも多く、予想外のトラブルやストレスに見舞われることも珍しくありません。
この記事では、実際に海外生活をスタートした家族のリアルな体験談を交えながら、準備段階で苦労したこと、やっておいてよかったこと、失敗から学んだことを詳しく紹介していきます。
ビザ申請は“情報の海”との戦い

体験談①:必要書類が二転三転、何度も大使館へ
オーストラリアに赴任が決まった私たち家族。最初にぶつかったのは、家族ビザ(dependent visa)の申請でした。
公式サイトを見ながら準備していたのですが、書類の記載方法や証明書の内容について細かい指定があり、しかも提出直前に「最新のフォームに変更されている」と言われてやり直しに。
出発3ヶ月前、家族ビザの書類を提出しに大使館へ。ところが「フォームが最新じゃない」と受付窓口で言われ、帰宅して再記入し、翌週また提出。さらに2週間後、「証明写真の背景がNG」と突き返され…
結局、3回も足を運び、子どもたちは待合室でぬりえに飽きて号泣しました。
対応策:経験者ブログと専門家のWチェック
役所や大使館のサイトだけでなく、実際に同じビザを取得した人のブログが非常に参考になりました。
また、移住サポートを行っている行政書士さんに事前チェックを依頼することで、抜け漏れが減り、精神的にも余裕が持てました。
英文書類の準備に泣いた
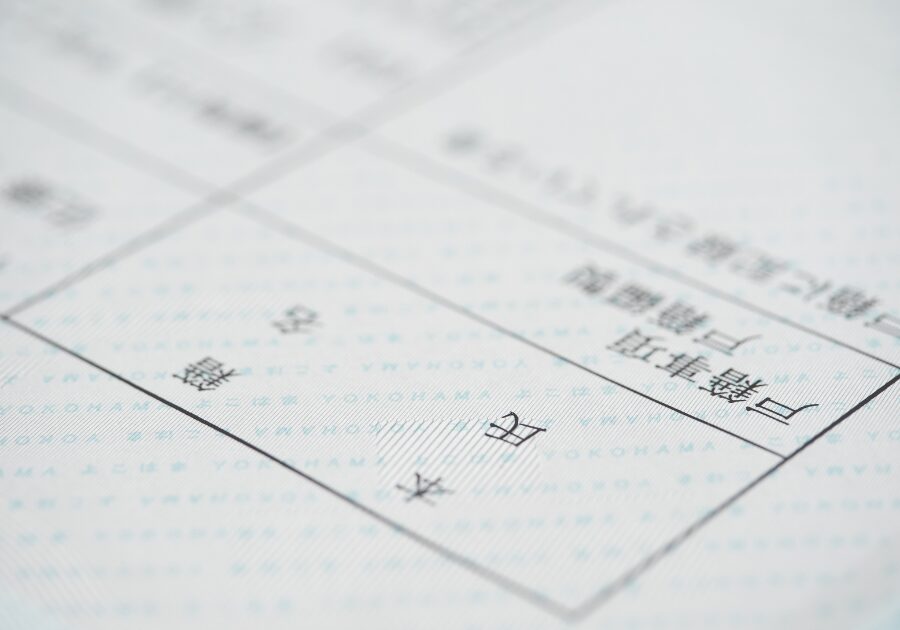
体験談②:出生証明書・戸籍謄本の英訳がネック
子どもを連れてドイツに渡航する際、「出生証明書の英訳付き提出」が求められました。
母子手帳では代用できず、戸籍謄本を英訳した上で、翻訳者の署名入りで提出する必要がありました。
出生証明と戸籍謄本を英訳し、知人翻訳者にお願いしたのですが「正式な認証がない」と受理されず。3回も資料を戻された末、JACI登録翻訳者に依頼し、公証役場でも認証。手元には「英語+証明済」の書類が揃い、ようやく入国もスムーズに。
対応策:JACIやJETRO認定翻訳者に依頼
結局、日本翻訳者協会(JACI)に登録している認定翻訳者を通じて、証明書を英訳してもらいました。費用は高めでしたが、正式書類として認められ、スムーズに受理されました。
英訳書類は、公証(Notarization)が必要になる場合もあるので、国ごとの要件を要チェックです。
保険の選択肢が複雑すぎる

体験談③:駐在員保険か、現地加入か?
アメリカ赴任が決まり、会社側から「任意で民間の駐在員保険に加入してください」と言われたものの、種類が多すぎて選べず。
現地での医療費が非常に高いことを考えると、しっかりした保険に入りたい。でも高額保険に加入すると、家族全体で年間80万円以上の出費に……。
どこまでカバーすべきか悩み続けました。
対応策:保険比較サイト+既加入者の口コミ
最終的には、海外保険の比較サイト(たとえば「たびほ」や「グローブパートナー」など)を使い、複数社のプランを比較。
さらに、実際に加入している駐在員ママのSNS投稿や口コミを参考に、「緊急搬送・通院・歯科あり」「妊娠関連サポートあり」のプランに絞り込めました。
子ども関連の書類も油断禁物

体験談④:予防接種証明で入園拒否!?
現地校に入園するには、予防接種履歴の提出が必須。でも、日本の母子手帳だけでは内容が伝わらず、「正式な接種証明がないと入園できない」と言われました。
慌てて日本の小児科に連絡して、英訳付き証明書を発行してもらうことに。
しかし、英訳に時間がかかり、結局入園が2週間遅れてしまいました。
対応策:出発前に医師と“英文セット”を用意
我が家では、これ以降の渡航では必ずかかりつけ医に「英訳の予防接種証明」「定期健康診断結果」「アレルギー情報」などを英語で発行してもらっています。
クリニックによっては書式のテンプレートを持っているところもあり、早めに相談しておくのがカギです。
日本側の手続きも盲点だらけ
体験談⑤:住民票の“除票”を出し忘れて大混乱
海外移住の際に必要な「住民票の除票」を出さずに渡航してしまい、マイナンバーが失効、税金関連の書類が届かないなど、日本側の行政手続きでも問題が発生。
一時帰国時に役所で一から説明し直し、手続きに半日かかることも。
対応策:出国チェックリストを作る
「転出届」「国民健康保険の脱退」「年金関連の通知」「子どもの学校への転校届」など、日本国内の手続きもまとめて出国前にリストアップ。
スマホのリマインダー機能やGoogleスプレッドシートで家族と共有して、抜け漏れがないよう管理しました。
最後に:海外渡航は“情報戦と根気”の連続
ビザ、保険、書類手続き。どれも一筋縄ではいかず、特に子連れや初めての渡航の場合、戸惑うことも多いです。
しかし、経験者の声やSNS、専門家のアドバイスを取り入れることで、事前に備えられる部分も格段に増えます。
最も大切なのは「わからないことを自分だけで抱え込まないこと」。
この記事の体験談が、これから海外に出る皆さんの手続きのヒントや安心材料になれば幸いです。
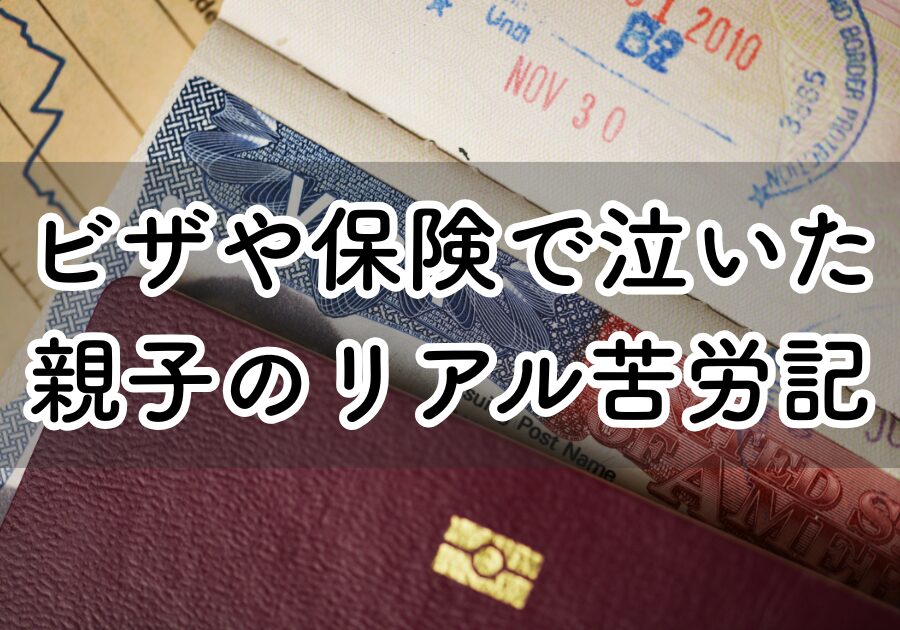
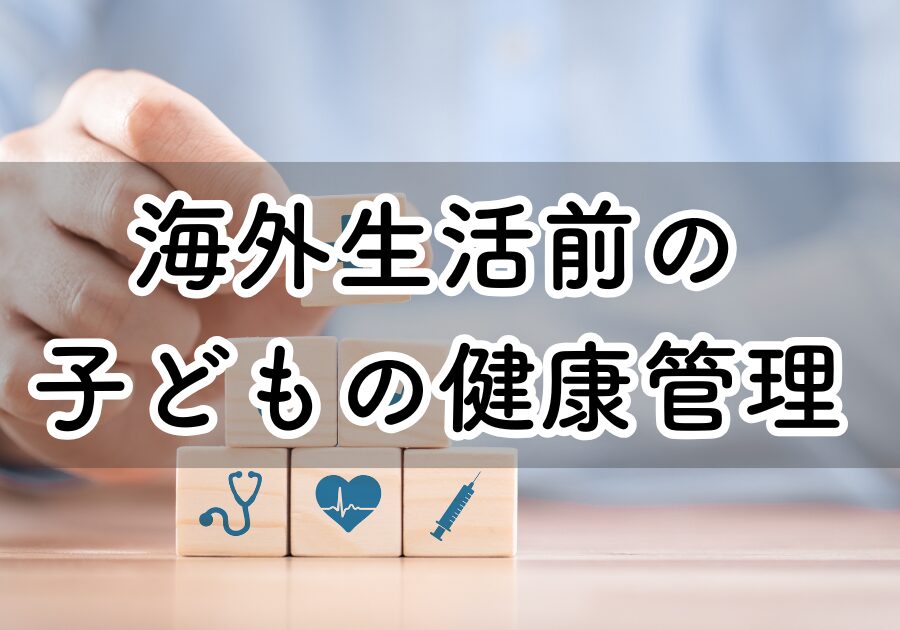

コメント