
この記事は私の母に当時のことを振り返って執筆してもらいました!
アメリカの現地校に転校したわが子が最初に直面したのは、言葉の壁よりも「友達関係をどう築くか」でした。
新しい環境に入るとき、周囲はすでに輪ができあがっているため、途中から加わることは大人にとっても簡単ではありません。ましてや十代前半の思春期にある子どもにとっては、大きな勇気が必要でした。
私自身も、毎朝送り出すたびに「今日は孤立しないだろうか」と胸を締めつけられるような気持ちでした。親としてしてやれることは「代わりに友達を作ってあげる」ことではなく、子ども自身が勇気を出すための支えになること。
そのことに気づいてから、私たちのサポートの仕方は大きく変わっていきました。
入学初日の朝——「これで浮かないかな」

登校初日の朝、子どもは早く目を覚ましていたのに、なかなか部屋から出てきませんでした。やっとリビングに降りてきても、口数が少なく、朝食のトーストをほとんど手つかずのまま。私が「緊張してるの?」と声をかけても「別に」と返すだけ。その表情は、普段なら冗談を言うときのような余裕はなく、こわばったままでした。
一番時間がかかったのは服装選びです。制服のない学校なので、何を着るかが“第一印象”を決めてしまうように思えたのでしょう。白いシャツを着ては脱ぎ、パーカーを羽織っては鏡の前でため息。結局シンプルなフーディにジーンズを合わせましたが、姿見の前で何度も「これで浮かないかな」とつぶやいていました。その声を聞きながら、思春期特有の繊細さと、自分の立ち位置を強く意識する年齢なのだと痛感しました。
車に乗り込んでからも、子どもは窓の外をじっと見つめて、私の質問にほとんど答えませんでした。信号待ちのとき、ハンドルを握る私の視界の端に、ぎゅっと握られた子どもの手が見えました。爪が食い込むほど拳を握りしめ、小さく震えているのに気づいたとき、胸の奥がきゅっと締めつけられました。
教室に入った瞬間——自分だけ取り残されたような感覚
学校に到着すると、担任の先生が笑顔で迎えてくれました。私も安心させようと「大丈夫だよ」と声をかけましたが、子どもは小さくうなずくだけ。
教室のドアが開いた瞬間、空気ががらりと変わったように感じました。中ではすでに笑い声が飛び交い、机ごとに輪ができあがっていました。英語の早口で交わされるやり取りの中に、わが子は一人で立ち尽くしていました。周囲の賑やかさとは対照的に、その姿だけが切り取られたように見えて、私には時間が止まったように感じられました。
自己紹介の場面になり、練習してきた「My name is…」を口にしたときの声は、かすかに震えていました。クラスメイトから何か質問が返ってきたものの、速すぎて聞き取れなかったのか、子どもは目を見開いて一瞬固まってしまいました。そのわずかな間が、私には痛いほど長く感じられました。
カフェテリアの孤独——声の届かない空間
昼休み、どうしても気になって校内を歩いていると、広いカフェテリアの隅にひとり座る子どもの姿を見つけました。
部屋いっぱいに響く笑い声や食器の音、英語の会話の波。その中で、子どもは小さなテーブルに腰かけ、持参したサンドイッチを黙々と食べていました。背中は丸まり、視線は下を向いたまま。周りの賑やかさが届かないように、自分だけ別の空気の中にいるように見えました。
声をかけて輪に入りたい気持ちはあるのに、どうしていいか分からない。かといって堂々と一人を貫くほどの強さもない。そんな中学生の心情が、その姿勢から痛いほど伝わってきました。私は遠くから見ていることしかできず、胸が張り裂けそうでした。
本当の壁は「言葉」ではなく「入り方」

後から子どもに聞いた言葉が忘れられません。
「英語が分からないのも大変だけど、それより“どこに入ればいいのか分からない”方がつらい」
私はハッとしました。つまり壁は語学力そのものではなく、“輪の入り方”。声をかけるタイミングや立ち位置が分からないことの方が、孤独を深めていたのです。
そこで私が家で意識してやったことは、とても小さなことでした。
- クラス名簿を一緒に見て、まずは名前と顔を覚えること
- 「今日は誰と少しでも話せた?」と毎日聞く習慣をつくること
- 「Can I sit here?」「Do you want to work together?」など、“入り口の一言”を一緒に練習すること
最初の頃は「今日も誰とも話さなかった」と落ち込む日が続きました。でもある日、「“Hi”って言えた」とうれしそうに話してくれたとき、その小さな一言がどれほど大きな一歩だったかを思うと、涙が込み上げました。

母が毎日のように一緒に練習してくれたことを、覚えています
中学生ならではの放課後の関わり方
小学生の頃なら「遊ぼう」と言えばそれで仲良くなれましたが、中学生になると関係の築き方はもっと複雑です。「誰とランチを食べるか」「誰と同じ班になるか」「放課後に誰と過ごすか」——それが日々の立ち位置を決めるような気がするのです。
そんな中、わが子にとって大きな転機となったのは、クラスメイトから「今度映画に行かない?」と誘われたことでした。帰宅してから「行きたいけど、何を話せばいいか分からない」と言ったときの不安そうな表情を、今も覚えています。送り出す私も不安でいっぱいでした。
けれど迎えに行ったときの第一声が「めっちゃ楽しかった!」だったのです。その笑顔を見た瞬間、私の方が泣きそうになりました。
親がやりすぎない勇気

子どもがひとりでいる姿を思い出すと、何度も「助けてあげたい」と思いました。でも、私が手を出してしまえば、子どもが自分の力で乗り越えるチャンスを奪ってしまうのだと気づきました。
だから私は意識して、
- アドバイスは子どもが求めてきたときにだけする
- 普段はただ話を聞き、受け止める
- 行き詰まったときは、担任やカウンセラーに相談し、環境を整えておく
という姿勢を続けました。

おわりに:友達づくりは“親子の共同作業”
海外での生活は、子どもにとっても親にとっても未知の連続です。特に中学生の「友達づくり」は、自分の居場所をどう築くかに直結する大きなテーマでした。
けれど、親が隣で見守り、ときに支え、ときに一歩下がって寄り添うことで、子どもは確実に自分の世界を広げていきます。
親ができるのは、子どもの前を引っ張ることではありません。安心して踏み出せる“空気”をつくること。
その一歩を支えた体験が、同じように海外で奮闘するご家庭にとって少しでも力になればと思います。

この記事が駐在生活のサポートになれば嬉しいです!
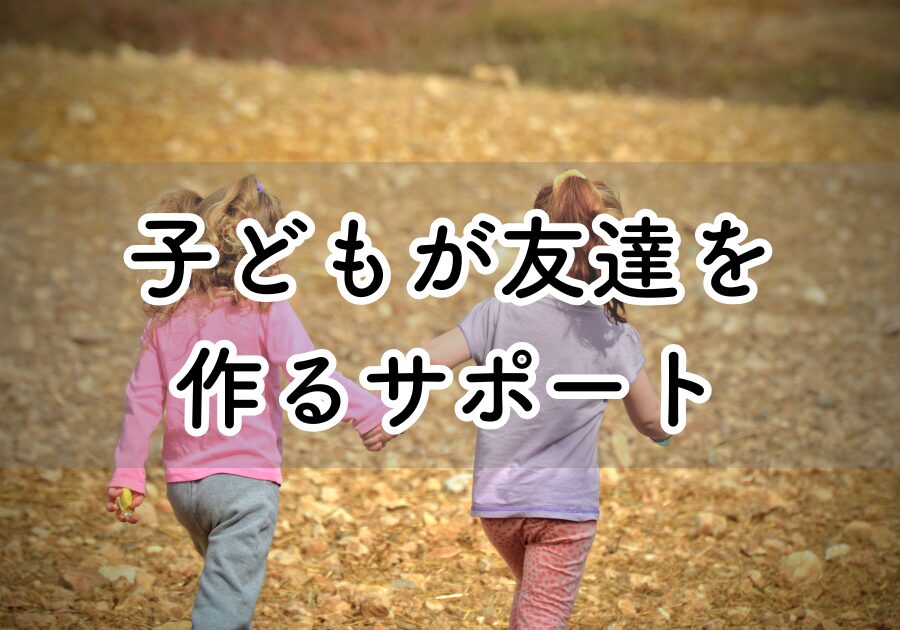
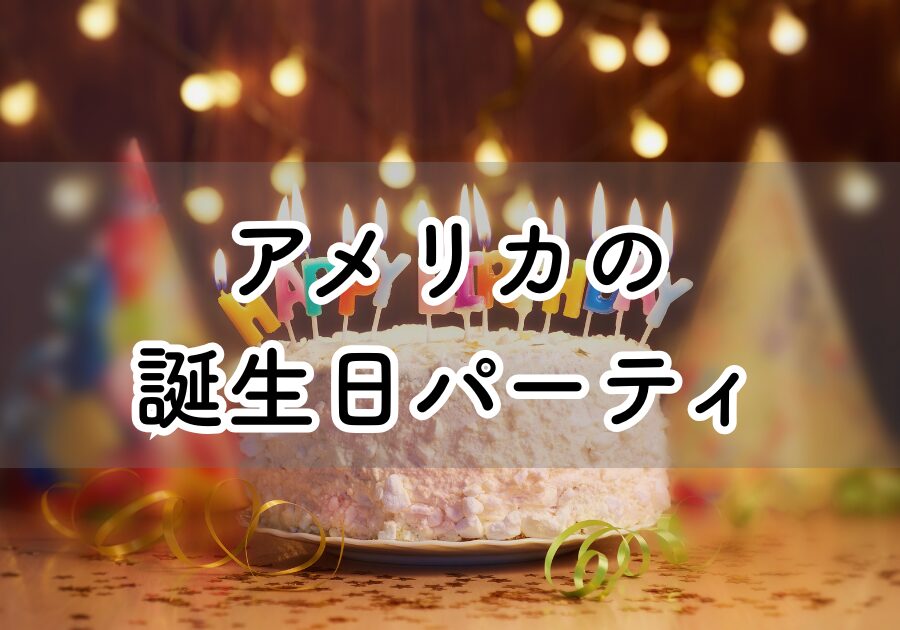
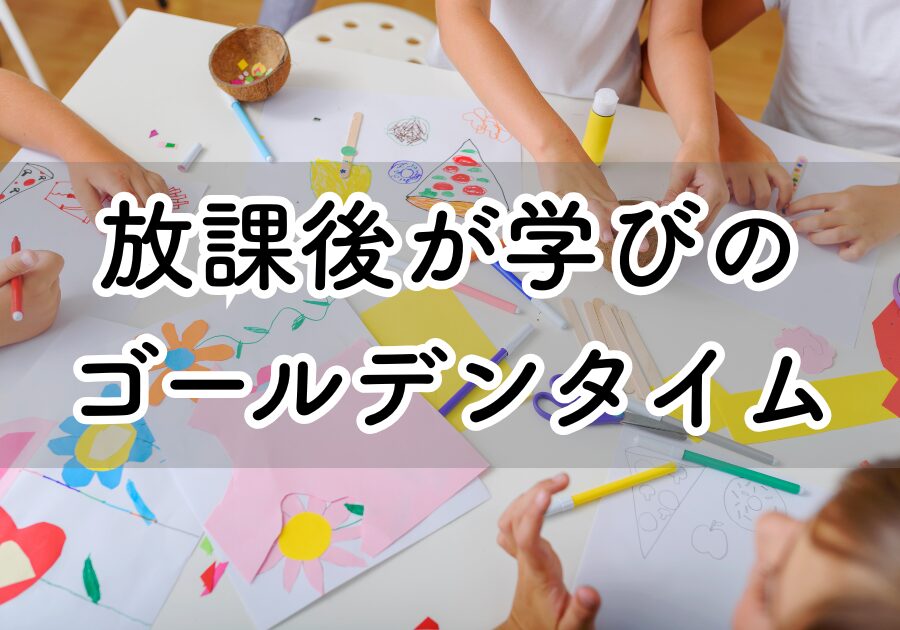
コメント