
この記事は、私の母が子育てをしながら駐在した経験をもとに記事を執筆してもらいました!
初めて海外駐在が決まったとき、「子どもの成長はここでどう変わるのだろう」と期待と不安を胸に飛び立ちました。あの静かな現地の住宅街で、予想もしなかった激しい親子のぶつかり合いが始まるなんて、当時の私はまだ知りませんでした。
私自身、家族で海外に暮らし、現地の子どもたちや日本人家庭の親子関係を間近で見てきました。反抗期の現れ方やタイミング、親子の距離感は、文化や環境によって大きく変わるものです。
本記事では、私や周囲の体験談、現地の子育て文化を交えながら、海外生活と子どもの反抗期の関係について掘り下げていきます。
反抗期は「自立」のプロセス
反抗期はなぜ起こる?
反抗期は、子どもが親や大人の価値観に疑問を持ち、自分の考えや生き方を模索し始める大切な時期です。親への反発は「自分らしさ」を確立するための健全なステップであり、どの国の子どもにも共通する成長の通過点です。
私自身、子どもの「なんで?」「いやだ!」という言葉に戸惑いながらも、これが自立への第一歩だと感じてきました。

私の反抗期のマックスは高校2年生くらいでしたね・・・笑
反抗期のタイミングや現れ方は国によって違う?
日本で暮らしていた頃、娘のイヤイヤ期といえば「自分でやりたい!」と泣き叫ぶ姿が日常の一コマでした。
ところが現地の学校に通い始めて数年後、今度は日本とは違う「目立たぬ反抗」が始まりました。言葉より態度――深夜までドアを閉めきり、私の呼びかけに無言でイヤホンを外す仕草。それがとてつもなく遠くに感じた瞬間でした。
例えばドイツでは、小学校高学年で一度強い反抗期があり、その後思春期に再び違った形で反抗が現れることも。アメリカやヨーロッパでは、親子のコミュニケーションが多く、感情表現が激しくても「親子の絆」は強いままという家庭も多いです。
海外生活が子どもの反抗期に与える影響

異文化体験が「反抗期」を遅らせることも
異文化環境で育つ子どもは、さまざまな価値観やルールに触れることで、自分の「基盤となる価値観」が揺らぎやすくなります。
日本のように「みんながこうする」という共通認識が薄れるため、何に反発すればいいのか分からず、反抗期が遅れるケースもあります。実際、私の周囲でも、海外で育った子どもが日本に帰国してから急に反抗的になったり、20代になってから親と激しく衝突する例も見られました。
多文化環境での「自己主張」と「反抗」の違い
英語圏では「反抗期」という言葉があまり一般的ではなく、「自己主張」や「独立心」として肯定的に受け止められる傾向があります。
アメリカのホームルームで娘が先生に「ここは自分に合わない」と訴えたとき、先生は「素晴らしい!自分の意見を持てるのは誇りだ」と拍手していました。その様子に驚きつつ、反抗ではなく「成長の証」として評価する現地流の子育てを実感した瞬間です。
私も現地の先生や親たちが、子どもの主張を一人の人格として尊重し、対話を重ねている姿に感銘を受けました。

確かに、アメリカの学校生活では、「自分の意見を主張すること」が必ず求められます。それができないと、むしろ「自分がない人」というレッテルを貼られてしまうことも・・・
価値観の多様性がもたらす親子の葛藤
異文化の中で育つことで、子どもは「日本の常識」と「現地の常識」の間で揺れ動きます。
「みんな同じ制服を着て、列に並ぶ」のが当たり前だった日本。私が「こうしなさい」と言うと、娘は「こっちの学校は違うんだから」とテーブルから立ち上がってしまう。
現地の友達は自由に意見を主張し、娘が「自分もそうなりたい」と悩んでいるのが伝わってきて、私も迷いながら見守りました。
私も「日本ではこうするのが普通」と言った時に、「ここでは違う!」と強く反発された経験があります。親子で価値観のすり合わせに苦労するのは、海外生活ならではの特徴です。
体験談:海外で迎えた子どもの反抗期

言語や文化の壁が反抗の表現を変える
アメリカで暮らしていた時、娘が思春期に差し掛かり「あ~言えばこう言う」状態に。日本語での悪口や反抗的な言葉が少ない分、英語で自己主張を強めるようになりました。
現地の友達との関係や学校生活でのストレスが家で爆発することもあり、親としては「どう受け止めればいいのか」悩む日々が続きました。

当時のことを思い返すと、とにかく学校の勉強が大変で、そもそもストレスが多かったように記憶しています・・
反抗期が「遅れて」やってきたケース
知人の息子さんはオランダで穏やかに学校生活を送っていましたが、日本に戻った途端、「こんなルールばかりの生活は耐えられない」と怒りを爆発させました。
異文化での「自分探し」の反動が、帰国後に一気に噴き出したようです。
親子で何度も話し合い、「どの価値観を大切にしたいか」を一緒に考える時間を持つことで、少しずつ関係が改善していきました。
反抗期が「目立たない」まま過ぎることも
海外の子育て仲間の中には、「うちの子は反抗期らしい反抗期がなかった」という声も。
我が家の次女は、現地の自由な校風のおかげか、「反抗期ってどれだったの?」と思うほど感情の爆発がなく、気付けば「私の意見はこう」と自然に話し合える関係になっていました。家庭の中で日々小さな主張を受け止め、強い衝突を防げたのかもしれません。
親が子どもの意見や感情を日常的に受け止めていると、反抗期が「爆発」せずに済むという実感もあります。

私の妹はこのタイプだったかもしれません。特に親と衝突することもなく、スルッと多様な価値観に溶け込んでいたように思います。
親の対応:海外流と日本流の違い

子どもの反抗を「否定せず受け止める」姿勢
娘が泣きながら「放っておいて」と叫んだ夜、「あなたの気持ち、全部はわからなくても聞かせてね」とだけ伝えました。翌朝、そっとココアを差し出した私の手を、少しだけ娘が握り返してきた。それが新しい信頼の始まりだったように思います。
アメリカの家庭では、子どもが泣いたり怒ったりしても、親は毅然とした態度で見守りつつ、必要以上に干渉しないスタンスを取ります。私も「できると信じているよ」と声をかけることで、子どもが自信を持てるよう心がけました。
家族の時間とコミュニケーションの大切さ
海外では家族で過ごす時間が日本より長く、親子の会話やハグなどのスキンシップが多いのが特徴です。反抗的な態度があっても、普段のコミュニケーションがしっかりしていることで、親子の信頼関係が揺らぎにくいと感じました。
私も意識的に子どもと一緒に料理をしたり、散歩をしたりする時間を増やすことで、心の距離を縮める努力をしています。
反抗期のトラブルと社会的リスク
アメリカでは、反抗期が家の中だけでなく、ドラッグやアルコール、危険な行動として表面化するケースも。
現地の親たちは、子どもが問題行動を起こした時にすぐに専門家やカウンセラーに相談することが一般的です。私も現地校のカウンセラーと連携し、子どもが悩みを抱え込まないようサポート体制を整えました。
親ができること・乗り越え方のヒント

価値観のすり合わせと「対話」の重要性
海外生活では、親子で価値観がぶつかるのは自然なことです。「なぜそう思うの?」「あなたはどうしたい?」と子どもの気持ちを聞き、親の考えも率直に伝えることで、対話を重ねていくことが大切です。
私も「日本と現地、どちらが正しいか」ではなく、「どう折り合いをつけるか」を意識してきました。

母と喧嘩した時、最後は自分の話をゆっくり聞いてくれたことを思い出します。自分の味方はここにいるんだ、という安心感につながったと感じています。
親自身も柔軟に変わる
異文化の中で子どもが成長するように、親も固定観念を手放し、柔軟に考えることが求められます。現地の子育てスタイルや価値観を学び、必要に応じて取り入れることで、親子の関係がより良いものになりました。
孤立しないための「つながり」作り
海外での子育ては親も孤独を感じがちですが、日本人コミュニティや現地のサポートグループ、学校のカウンセラーなど、頼れるつながりを持つことが心の支えになります。私も悩んだ時は同じ立場の親と話すことで、気持ちが楽になりました。

私自身、毎週土曜日の日本語補習校の存在は、ほっと一息つける時間でした。
まとめ:海外生活がもたらす親子の成長
海外生活は、子どもにとっても親にとっても「自分らしさ」や「多様な価値観」と向き合う貴重な時間です。反抗期の現れ方やタイミングは一人ひとり異なりますが、異文化の中で育つことで、親子ともに新しい発見や成長のチャンスが広がります。
海外での反抗期には「戸惑い」も「涙」もたくさんありました。でも、ぶつかり合うたびに新しい親子の形が生まれた実感があります。
「こうあるべき」を一度置き、互いの「らしさ」を少しずつ認め合う――それが異国の地で私たち家族が手にした一番の財産です。
おわりに
子どもの反抗期と海外生活は、時に悩みの種にもなりますが、見方を変えれば大きな成長のチャンスです。親も子も柔軟に、前向きにこの時期を乗り越えていきましょう。
本記事が、海外で子育てをするご家庭や、異文化の中で悩む親子のヒントになれば幸いです。

子どもの立場だとむしゃくしゃして、親と喧嘩しているだけという認識でしたが笑、親からすると、いろんなことを考えて乗り越えてくれたんだなということがわかります。感謝しきれません・・
ぜひ海外に子連れで行かれる方は、当記事を参考にされてくださいね。
(※本記事は筆者自身の体験および複数の海外在住者・親子の声をもとに執筆しています。内容の一部は個人の感想です。)
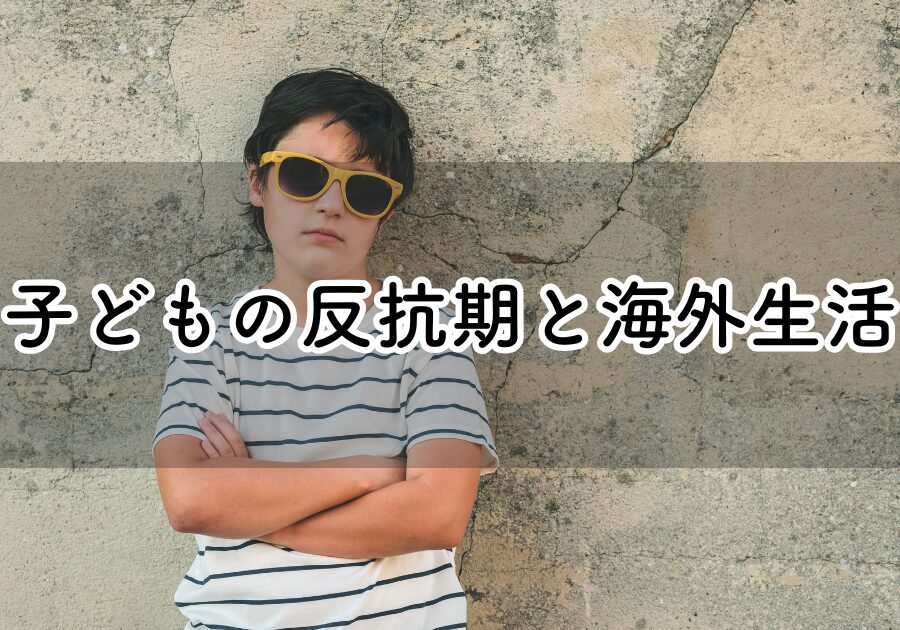
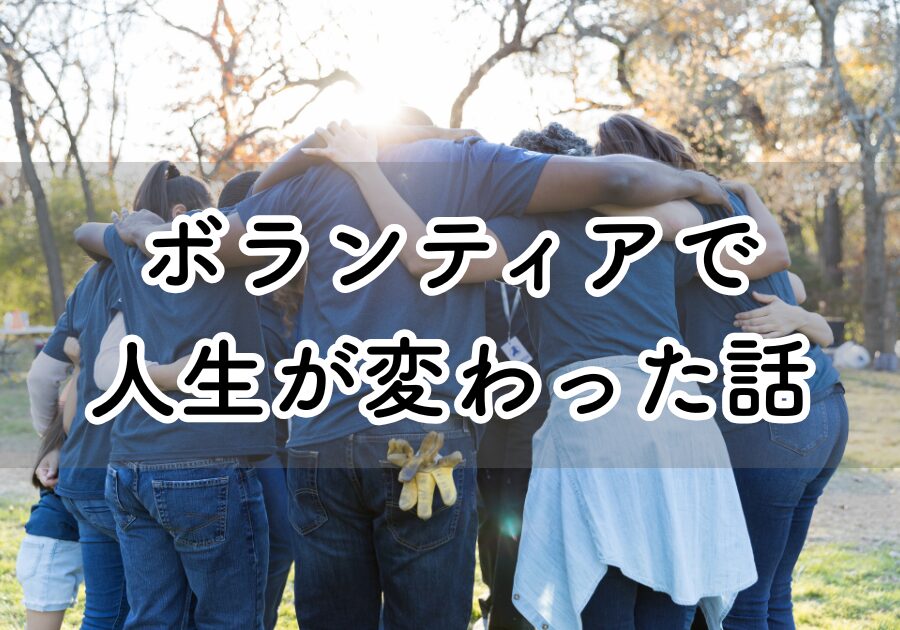
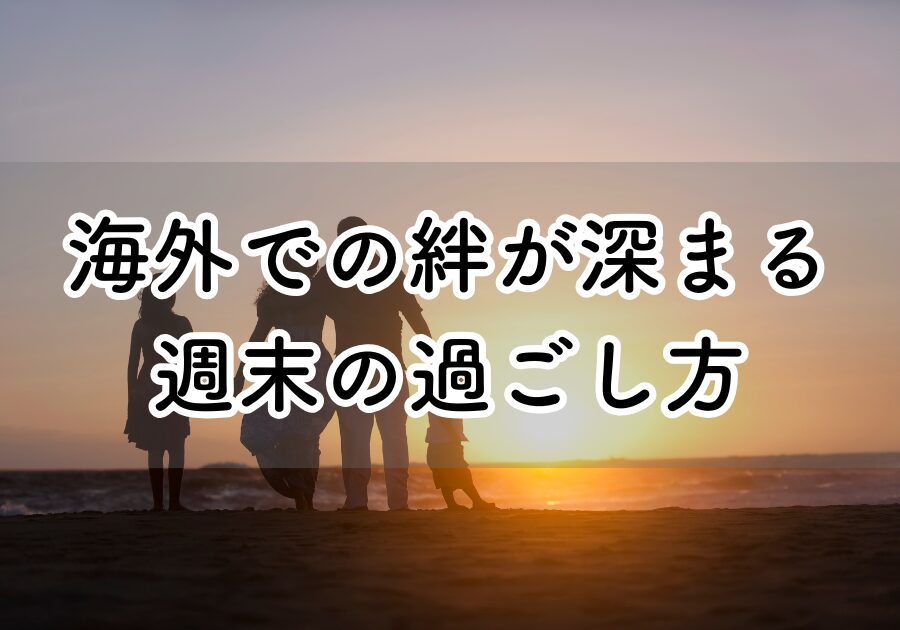
コメント