
この記事はニーチェの母に、当時の気持ちを思い出してもらいながら、執筆してもらっています
アメリカ移住後の数か月、私は娘との沈黙に戸惑い、毎晩「今日もまた“別に”だけだったな」と反省しながら眠る日々でした。子どもが抱えているものに気づけず、母親としてどうしたらよいか本当に悩みました。
引っ越し前は夕食のたび、「今日の給食さ、面白いことがあってね」と話が止まらなかった娘。けれど渡米後、食卓は沈黙が増えました。私が「学校どうだった?」と聞くと、ほとんど毎日「うーん、別に」と返すだけ。何度も胸が締めつけられ、一人で泣いてしまった夜もあります。
この記事では、そんな私たち親子が実際に経験した「会話の減少」と、それをどうやって乗り越えたのか、実際に効果があった工夫を体験談とともに紹介します。
会話が減るのは“悪いこと”とは限らない
最初にお伝えしたいのは、会話が減ること自体が必ずしも悪いわけではないということです。新しい環境に適応する過程で、子ども自身が言葉にできない不安やストレスを抱えていたり、英語環境で頭をフル回転させて疲れていることもあります。
我が家では、渡米直後こそワクワクと不安が混ざった興奮状態でしたが、しばらくすると娘(当時中1)の口数が一気に減りました。何を聞いても「分かんない」「別に」と返され、会話が続かない日々が続きました。

そんな日もあったかもしれません・・・笑
原因を“問い詰めずに”見守る姿勢

ついつい「どうして話してくれないの?」「何があったの?」と問い詰めたくなってしまうのが親心ですが、それが逆効果になることもあります。私自身、最初は「なんとか話させなきゃ」と焦ってしまい、余計に娘の態度が閉じてしまった経験があります。
その反省から、意識したのは“待つこと”。毎日決まった時間に「今日はどんなことがあったの?」とだけ聞いて、答えがなければ「そっか、じゃあまたあとで教えてね」と軽く返すようにしました。
無理に言葉を引き出そうとしないことで、子どもが「話したくなったときに話せる」安心感を持てるようになった気がします。

確かに、ある時から深く追求されることがなくなって、気が楽になりました。母なりの工夫があったんですね・・・!
会話の“きっかけ”をつくる日常の工夫

言葉での会話が難しいときは、言葉以外のコミュニケーションからスタートするのも有効でした。以下、我が家で取り入れた工夫をいくつかご紹介します。
一緒に料理をする
ある日、娘が珍しくキッチンを覗いてきたので、「一緒に味噌汁作ろうか」と誘いました。具材を切りながら、「今日はどの味噌にしようかな」「日本の味懐かしいね」と、料理の香りに包まれながらぽつぽつと言葉が出てきたのが嬉しくて。手を動かすと心もほぐれる、この体感は忘れられません。
作業を通じて手が動くと、口も動きやすくなるというのは本当でした。
毎晩の“3つのよかったこと”
無理に話させず、でもほんの少し会話のきっかけが欲しくて、「今日、良かったことを一つだけでも教えてくれる?」と、最初は一つから始めました。
最初の数日は黙り込むだけ。でも、数週間後、「今日は新しい単語覚えたよ」と小さな声で返してくれた日、何よりも嬉しい瞬間でした。

これが、鬱陶しいと思う頃もありましたが、今では会話のきっかけになるいい思い出です
1日1個“英語クイズ”を出す
「ママが今日覚えた英語、わかるかな?」とクイズ形式で英語を出題。子どもが得意な分野に絡めることで、「え、それはね……」と会話が自然に始まりました。知識を共有することが会話の種になります。
会話が“なくてもいい時間”を大切にする
ある日、テレビを一緒に観ていたときにふと感じたのは、「会話がなくても、一緒にいるだけで安心できる時間もある」ということです。
言葉はなくても、同じソファに並んでドラマを見る時間。「こんな静けさも、安心できる親子の証かもしれない」と初めて思えたのは、娘の隣で何も話さずに笑い合えたあの日でした。
共通の趣味(ゲーム、読書、音楽など)を持ち、黙っていても心がつながっているという感覚を共有することで、言葉に頼らない信頼関係が築けることを学びました。
手紙やメモで“間接コミュニケーション”
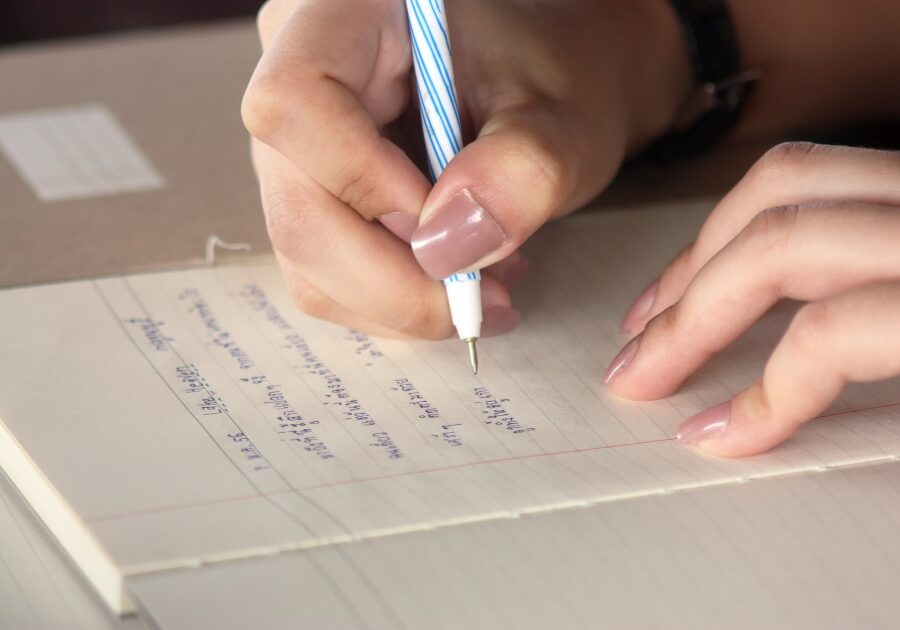
言葉でうまく気持ちを伝えられないときは、手紙やメモも活用しました。たとえば、
- 朝の支度中に「今日も頑張ってるね!」と短いメモを渡す
- ランチボックスに手書きのメッセージをそっと忍ばせる
そんなちょっとした工夫でも、「ママは見てくれてる」という安心感につながるようです。返事がないことも多いですが、後日ぽろっと「今日のメモ、うれしかった」と言ってくれることもありました。

慣れない海外での学校生活の中、母が作ってくれたお弁当に日本語でお手紙が入っていたのは、安心しましたし嬉しかったです!今でも大事に取ってあります。
定期的に“親子でだけ”の時間をつくる

兄弟がいる場合などは、特に意識して「一対一で話す時間」を持つようにしました。週末の買い物ついでにふたりきりでカフェに寄ったり、夜の散歩を一緒にしたりする中で、普段言えない本音が出てくることもありました。
あえて「何かを話させる」のではなく、ただ“ふたりで過ごす”という体験が、心の距離を縮めてくれます。
「会話が減る時期」も成長の一環と捉える

思春期や新しい環境への適応期には、どうしても会話が減る時期があります。それは親子関係が悪化したわけではなく、子ども自身が「自立」し始めているサインでもあります。
大事なのは、親の側が不安になって“無理に戻そう”としないこと。
「この子なりに、いま心の整理をしているんだな」と信じて見守ることで、また自然と会話が戻ってくる日がやってきます。
まとめ:言葉に頼らない“つながり”を育てる
会話が減った毎日は戸惑いだらけ。でも、沈黙に寄り添い、小さなメモや一緒に過ごす時間を重ねるうちに、「この静かな時期もきっと無駄じゃない」と信じられるようになりました。
また、子どもとの関係性は、言葉の数ではなく“気持ちの届き方”にあります。
一緒に過ごす時間、そっと見守るまなざし、小さなメモ…そうした日々の積み重ねが、親子のつながりをより深く、強いものにしていくと信じています。
会話が戻る日は、きっともうすぐそこです。

母なりの葛藤や工夫を感じることができ、改めて感謝しかありません。皆さんも、もしお子さんが同じ境遇になったとしても、本記事を参考に「心の距離」を縮めて見てくださいね。


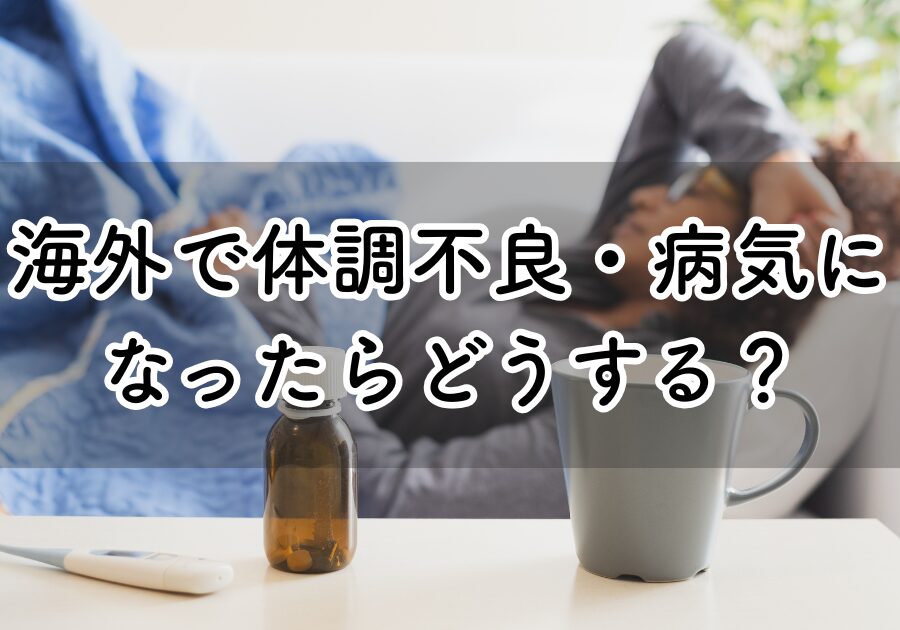
コメント