「なんで私たちがアメリカに?」と、飛行機の窓から見えたシカゴの広い空をいまでも覚えています。
突然決まった家族の海外移住。私はまだ中学1年、英語は自己紹介さえもおぼつかず、未知の文化に不安しかありませんでした。
渡米直後の数カ月間は、学校の廊下を歩く足取りさえ重く、「今日も誰ともしゃべらずに1日が終わるんだろうな」と心の中でため息ばかり。家族も同じように、言葉の壁や生活の違いに戸惑い悩んでいました。
バスの乗り方ひとつ、教室での会話ひとつ、何もかもが未知で、英語を聞き取ることすら満足にできませんでした。
そのようななかで、私たち家族にとって予想外の“救い”となったのが、地域で開催されるさまざまなイベントでした。そこには、言葉を超えて人と関われる空気があり、静かに、しかし確実に私の心をほぐしてくれる何かがありました。

ここでは、当時の私が実際に参加した地域イベントを、記憶の断片をたどるようにご紹介しながら、あの頃感じた戸惑いや発見、そして成長について綴ってみたいと思います。
ハロウィンパレードでのはじめの一歩

アメリカに来て最初の秋、私は地域のハロウィンパレードに参加しました。最初は乗り気ではありませんでした。というのも、仮装して人前に出ること自体に慣れていなかったうえに、見ず知らずの人たちの中で、英語が話せない自分がどう振る舞えばいいのかわからなかったからです。
それでも、両親に勧められて、私は意を決して家のクローゼットにあったマントと仮面を身につけて、街へと出かけました笑
通りに着くと、まるで別世界のような光景が広がっていました。家々のポーチにはオレンジ色のランタンが灯され、仮装した子どもたちの笑い声が夜風に乗って響いてきます。大人も子どもも、楽しむことに全力を注いでいるようでした。
10月の冷たい風が吹き抜ける夜、一歩を踏み出す勇気がなかなか出ませんでした。仮装パレードの行列に加わる直前、母が「大丈夫、失敗しても楽しもう」と背中を押してくれたのですが、私は「失敗したらどうしよう…」と心配ばかり。
けれど、パレードの途中で出会った小さな女の子が、「Nice costume!」と全力の笑顔で声をかけてくれた瞬間、頑なに閉じていた心がいっきにほぐれました。それまで緊張でこわばっていた顔が自然とほころび、「Thank you」と返せたことに帰宅後、小さくガッツポーズしていた自分がいました。
このささやかな出来事が、アメリカという大きな世界の中に「自分の場所」を感じる最初のきっかけだったように思います。
その瞬間、自分の中の緊張がふっとほどけるのを感じました。

完璧な英語を話せなくてもいい。間違えても笑われない。ただ、そこにいて、一緒に楽しもうとする姿勢があれば、それだけで十分だったのです。
サマーフェスティバルでの多国籍な出会い

翌年の夏、地域の公園で開催されたサマーフェスティバルにも足を運びました。広大な芝生の上に、色とりどりのテントとフードトラックが並び、空には綿菓子のような雲が浮かんでいました。
私はTシャツにジーンズというラフな格好で、手にレモネードを持ちながら、人々の間をゆっくり歩きました。
会場には未知の香りや音が溢れていて、たとえば本場インド人が丁寧に作ってくれたカレーのスパイス、メキシコの家族が踊る陽気な音楽、チャイナタウンから来た獅子舞…まるで異世界に迷い込んだようでした。
その中でも印象的だったのは、韓国料理の屋台で初めて食べたビビンバ。並んでいるあいだ、屋台のおばさんが「あなた、もしかして引っ越してきたばかり?」と気さくに話しかけてくれ、「うまくいかない日もあるよ。でも今日は思いっきり楽しみなさい」と優しく励ましてくれました。
その言葉は、ひとりぼっちの私を心から励ましてくれる魔法のように感じました。
その言葉が、なぜか心に深く残りました。英語で流暢に話す必要も、何かを証明する必要もない。

ただ、今いるこの場所と時間を楽しめば、それでいい。そう思えたとき、世界が一回り近くなったように感じたのです。
PTA主催のチャリティーバザーでの協力体験

中学2年のある日、学校の掲示板に「PTA Charity Bazaar Volunteer募集」というポスターが貼られていました。私はなぜかそのポスターから目が離せず、思い切って申し込むことにしました。自分にできることは限られているけれど、挑戦してみたいと思ったのです。
当日は朝から準備で大忙しでした。体育館の中に折りたたみテーブルがずらりと並び、手作りのお菓子やアクセサリー、本や古着が並べられていました。私は簡単な仕事から手伝いました。紙袋に商品を入れたり、お釣りを渡したりする中で、保護者の方々が「Good job」「You’re helping a lot」と声をかけてくれました。
イベント終了後、先生に「勇気を出してチャレンジしてくれてありがとう」と褒められ、今まで感じていた劣等感が少しずつ和らいでいくのを感じました。
地域の図書館イベントでのほっこり時間

慣れない週末、心が落ち着ける場所を探して通った先が地域の小さな図書館でした。
最初のうちは英語の絵本すら読めず遠慮がちに隅っこで座っていただけ。それでも何度も通ううちに、館内で開催される読み聞かせ会に顔を出すようになり、ボランティアのスタッフからは「今日も来たね!」と声をかけてもらえるようになりました。
たわいもない会話、ほんの短いやりとり。けれど、その積み重ねが“この場所の一員”だと自分を認めてもらえた気がして、孤独感が少しずつ溶けていきました。
地域イベントが生み出す“緩やかな関係”

アメリカでの生活は、日本のような濃密な人間関係とは異なる部分が多くありました。
けれど、地域イベントに参加してみてわかったのは、ここでは「無理に関わり合わなくても、顔を合わせたときに自然と笑顔を交わす」、そんな“緩やかなつながり”こそが重視されているのだということです。
その緩やかさがあるからこそ、居心地のよさがあり、孤立せずに済んだのだと思います。

助けを求めるとき、誰かが手を差し伸べてくれる安心感。誰かの名前を呼ぶと、笑顔で応えてくれる距離感。
それは、地域イベントで出会った人々の中に、確かに存在していました。
まとめ:地域イベントは交流の原点
振り返れば、新しい環境になじめず悩んでいた自分を救ってくれたのは、家族でもなく学校の成績でもなく、「地域の人たち」との何気ない小さな交流でした。
たとえ言葉に自信がなくても、イベント会場のあの明るい空気、見知らぬ人がくれる笑顔にふれて、私はこの街でたしかにつながりを感じられるようになりました。
無理に人に合わせる必要も、うまく立ち振る舞う必要もありません。「この場所が自分の居場所だ」と思えたことが、アメリカでの不安を乗り越えた最大の力になりました。

あの頃に見た景色や聞いた言葉は、今でも私の記憶の中で鮮やかに生き続けています。地域との関わりがあったからこそ、私はこの地で“ひとりじゃない”と感じることができたのです。
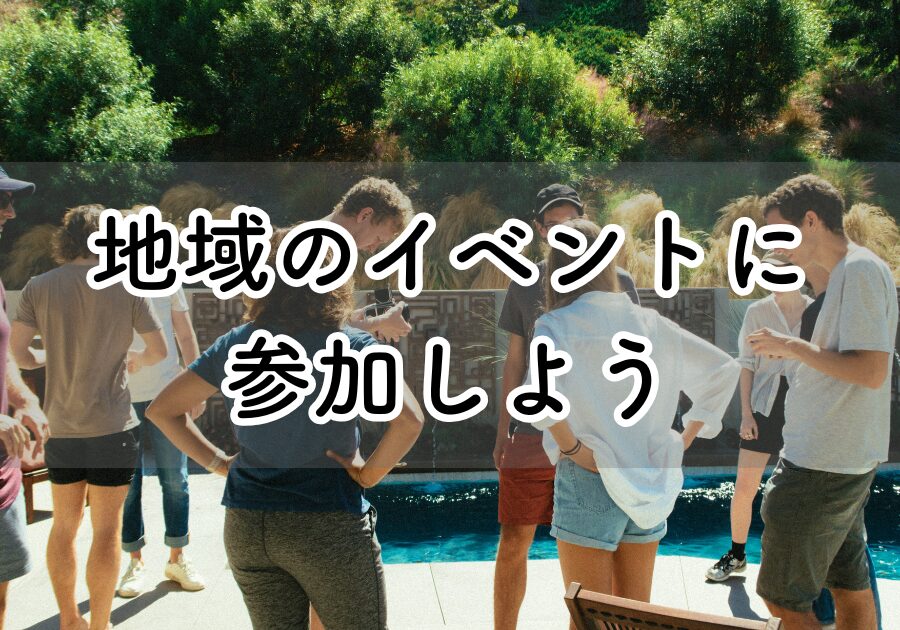
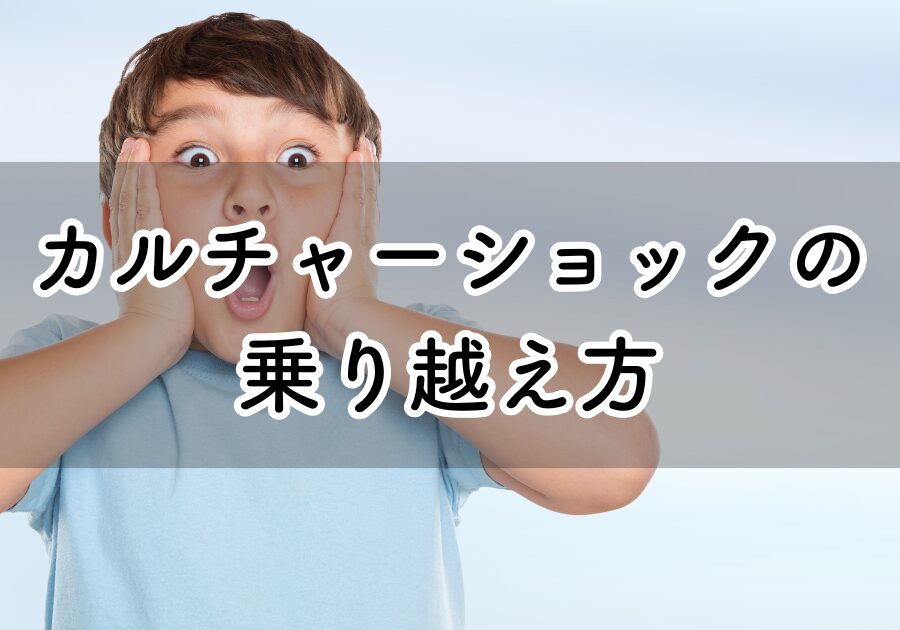

コメント