アメリカに移住して最初の数ヶ月、私の周りでは次々と「え、そうなんだ!?」と驚くような出来事が続きました。
家族の転勤で中学から高校までアメリカで過ごした私にとって、文化の違いは想像していた以上に大きく、日常生活のあらゆる場面でその深さと広がりに圧倒されることばかりでした。
ニュースやドラマで一通り知っていたはずのアメリカ文化ですが、実際に体験することで見えてきたのは、それぞれの習慣や考え方がどれほど異なり、どれほど独特であるかということです。
本記事では、私自身が経験したアメリカ生活の中で感じた“異文化ギャップ”をご紹介します。笑いを誘うような小さなエピソードから、思わぬ戸惑いや反省を伴う出来事まで、リアルな体験を通して学んだことをお伝えできればと思います。

アメリカにこれから渡米する方々、また既に住んでいる方々にも、きっと共感していただける内容だと思います。
スモールトーク文化に戸惑う

アメリカに到着して最初に感じた驚きは、「誰もがどこでも話しかけてくる」ことでした。
スーパーのレジ、エレベーター、近所の散歩中…と、まるですべての場面が会話の機会になっているかのようでした。

特に最初は、「そんなに話さないといけないの?」と不安になることもありました。
ある日、Trader Joe’sで買い物をしていたときのことです。レジで支払いを済ませようとした瞬間、店員さんがにこやかに「今日はこの商品、初めて買うの?これ、美味しいんだよ!」と話しかけてきました。
その時、私は驚きすぎて、少し動揺してしまいました。どう反応して良いのか分からず、「はい…」と小さく答えるだけで、無言でその後も手を動かし続けました。袋に商品を詰めながらも、「これで良かったのかな?」と心の中で自問自答していた私。
後で家に帰ってその出来事を父に話すと、「あれはちょっと無愛想すぎたかもしれないね」と指摘され、ハッとしました。
彼らのスモールトークが「礼儀」や「親しみ」の表れであることを理解したのは、それからしばらく経った後のことでした。

最初は驚きと戸惑いばかりでしたが、次第に「会話を交わすことが、相手に対する思いやりなんだ」と感じるようになり、その重要性を実感しました。
タイムマネジメントの“ゆるさ”に驚く
日本では、時間を守ることがとても大切にされています。遅刻はほぼ許されない文化です。しかし、アメリカではその「時間の厳しさ」に驚くことが多かったです。特に学校や習い事での集合時間が、思った以上に“アバウト”であることに最初は違和感を覚えました。
ある日、補習校の集合時間に私たちは時間通りに到着しました。時計を見てみると、ちょうどその時刻。ところが、教室の扉はまだ閉まっており、周りには誰もいませんでした。
周りの他の生徒も、まだ教室に入る様子がない…。ちょっと戸惑っていると、主催者の先生がにこやかに「遅れてきても大丈夫だよ!慌てなくていいよ!」と声をかけてくれました。
私はその言葉に驚き、「本当に?」と心の中で思ってしまいました。日本では考えられない、時間に対するこのゆるい感覚に最初は驚きましたが、徐々にアメリカでは「みんながリラックスしていること」が大切だという価値観が、少しずつ心地よく感じられるようになっていきました。
食事スタイルの違いにカルチャーショック

アメリカでの食事文化も、最初は驚くことが多かったです。特に外食時に、料理が一斉に運ばれるわけではなく、来た人から食べ始めるスタイルに戸惑いました。
ある日、現地の友人家族とランチに出かけた時のこと。私が待ちきれずに自分の料理が来るのをじっと待っていると、周りの人たちは次々と料理が運ばれると、すぐに食べ始めました。
その光景に、私は驚きました。「みんな待たないの?」と心の中で疑問を感じながらも、少しだけ様子を見守っていました。
後で友人に聞くと、アメリカでは「料理は冷めないうちに食べるのが当然」という考えがあることを知りました。

「いただきます」や「ごちそうさま」の文化とは全く異なる、食事を楽しむ新たな価値観を学んだ瞬間でした。
「空気を読む」が通じない!?
日本では、「空気を読む」ということが非常に大切にされています。相手の気持ちを察して行動する、ということが自然にできる文化に慣れている私には、アメリカでの「自己主張が必要」という文化が最初は驚きでした。
特に、何も言わずに黙っていると、気持ちが伝わらないどころか、むしろ「何も考えていない」と受け取られることもあるのです。
ある日、学校で行われた保護者向けのオリエンテーションイベントでのことです。私の担任の先生が進行をしていて、学校生活の重要な点を説明していました。
その中で、私は「ちょっとこれについては、こうしたほうがいいんじゃないかな?」と思う点がありましたが、日本の感覚で「みんなが気づいてくれているだろう」と黙っていました。周りは皆、積極的に質問をしたり、自分の意見をしっかり伝えていたのですが、私は言葉を発するのが怖くてそのまま様子を見ているだけでした。
イベントが終わり、担任の先生が個別に話す時間になったとき、私に「あなたはどう思ったの?」と声をかけられました。その瞬間、私は「言わないと、何も伝わらないんだ」と強く実感しました。
アメリカでは自分の意見をきちんと言葉にしなければ、ただの傍観者になってしまうということを痛感しました。

それからは、簡単なことでも自分の意見をしっかり伝えるよう心がけ、積極的に参加するようになりました。
“褒める文化”の威力

アメリカでは、褒めることがとても重要視されています。日本では、成果を出すことに対して謙虚でいるべきだという価値観が強いため、あまり大げさに褒められることは少ないのが現実です。
しかし、アメリカでは「褒めることで自己肯定感を育む」という考え方が浸透しており、どんなに小さなことでも大きな賛辞をもらえることが普通です。
中学生になり、アメリカの学校で初めて絵画の授業を受けた時のことを今でも鮮明に覚えています。私は日本で絵を描くことが得意だとは思っていませんでしたが、アメリカの美術の先生は、私が描いた絵を見て、「Wow! This is AMAZING! You’re so talented!」と目を輝かせながら何度も繰り返し褒めてくれました。
その瞬間、私は本当に驚きました。日本ではこんなに大げさに褒められることなんてなかったので、最初は「そんなに褒めなくても…」と思っていたのです。でも、クラスメートたちもそれぞれ自分の作品に対して同じように褒め合い、その後、私も自分の絵に対して少し自信を持つようになりました。
気づくと、アメリカの学校では、褒められることが自己肯定感を高め、自分を信じる力になるのだということを実感しました。

それ以来、私はどんな小さな成果でも大切にし、周りの人を褒めることの大切さを学びました
洗濯物は乾燥機、外には干さない
日本では、天気が良ければ外に洗濯物を干すのが普通でした。風に吹かれて、自然に乾く洗濯物が何となく気持ちよく感じられたものです。
しかし、アメリカに来て最初に驚いたのは、ほとんどの家庭が乾燥機を使い、洗濯物を外に干すことはほとんどないということでした。地域によっては、外に洗濯物を干すことが好ましくない場合もあるのです。
アメリカに引っ越してから間もなく、私は慣れ親しんだ日本のやり方で、母を手伝い、ベランダに洗濯物を干しました。
アメリカでは乾燥機が普通だということは理解していたものの、私は「せっかく天気もいいし、外に干した方が気持ちがいいだろう」と思い込んでいました。
しかし、数日後、近所の人から「洗濯物を外に干すことは、見た目が良くないと思う人も多いんだよ」と優しく教えてもらいました。その地域では、洗濯物を外に干すことが好まれないことが多いと聞き、驚きました。
その後、周りの家々を見てみると、どの家も外に洗濯物を干しておらず、乾燥機で簡単に済ませていることがわかりました。最初は「どうして?」と戸惑いましたが、アメリカでは生活のスタイルがそれぞれ異なることを学び、その後は乾燥機を使うことが当たり前になりました。
ハグ・握手・距離感の違い

アメリカに来て最初に驚いたのは、挨拶がとてもオープンで、身体的な距離感が日本とは全く異なることでした。
日本では、特に初対面の人と握手を交わすことはあっても、ハグをすることはまずありません。初めてアメリカに来た時は、挨拶でハグをする文化に慣れるのが本当に大変でした。
ある日、学校のイベントで新しい友達を作った時のことです。クラスが終わった後、帰り際にその友達が「じゃあね!」と言いながら、突然私にハグをしてきました。
その瞬間、私は完全に固まってしまいました。どうして良いのか分からず、体が一瞬、動きを止めてしまいました。その後、周りを見てみると、他の生徒たちは皆、自然にハグを交わしているではありませんか。
思わず「これがアメリカの文化なんだ…」と感じました。最初は本当に恥ずかしく、距離感が掴めずに戸惑いましたが、時間が経つうちに、アメリカではハグが親しみを表す普通の行動であることを理解しました
その後、別の友達と会った際も、「おはよう!」と言いながら、ハグをしてきたので、今度は少しだけスムーズに対応できた自分に驚きました。

最初は距離を感じていたものの、今では軽いハグや手を振るだけでも、友達との絆を深める大事なコミュニケーションだと感じています。
おわりに:ギャップは“違和感”で終わらせない
異文化ギャップを感じることは、どこの国に住んでいても避けられないものです。でも、それをただの「違い」として受け入れるのではなく、しっかりと「学び」に変えていくことで、私たちはどんどん成長できると実感しています。最初は驚きと戸惑いの連続だったアメリカでの生活も、今では自分なりのリズムができ、心地よく過ごせるようになりました。
これからアメリカで暮らす方々にとって、この記事が少しでも参考になり、心の準備ができる手助けになれば嬉しいです。
異文化の違いを楽しむことができるようになれば、それは新しい自分に出会うための素晴らしい機会となるはずです。

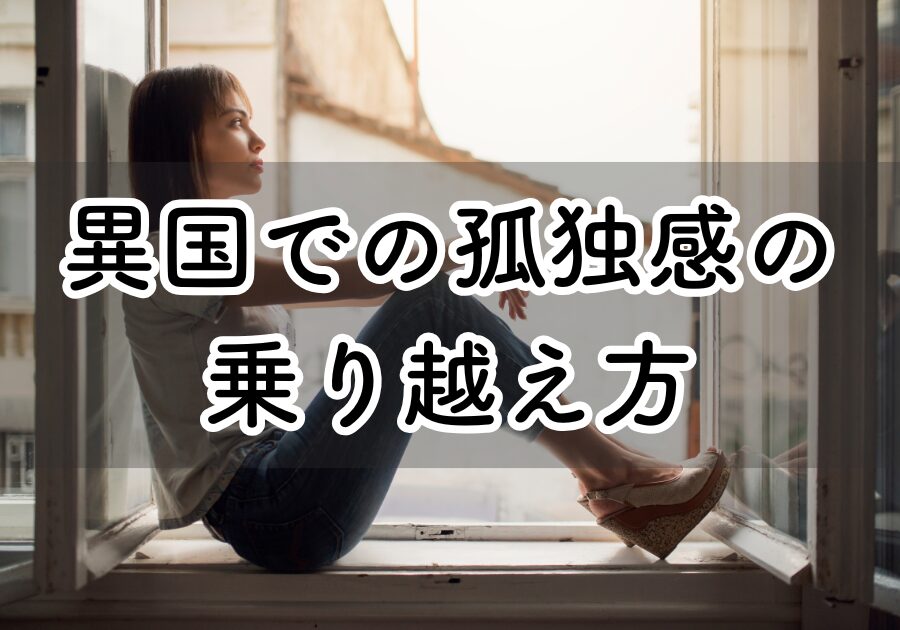
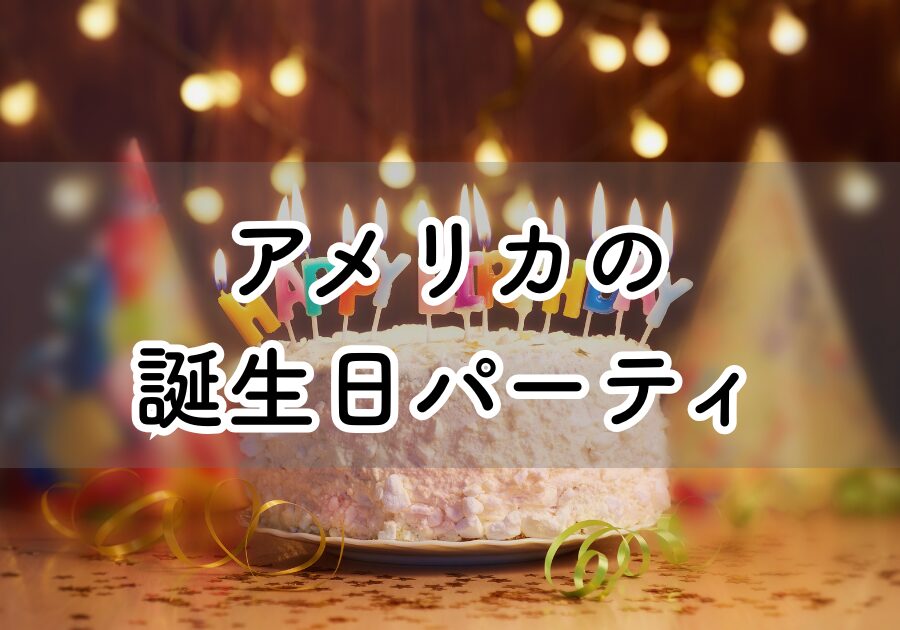
コメント