中学1年生でアメリカに渡った私は、最初の半年間、毎日が探検と戸惑いの繰り返しでした。
英語の授業についていくのも一苦労で、授業中に先生の冗談が通じないたびに、自分が「部外者」ように感じることもありました。
放課後になると、現地の中学生たちは自然に輪を作り、楽しそうに会話していますが、私自身はどう足を踏み入れて良いのか分からず、時々図書館に一人で座っていた思い出があります。
そんな生活のなかで、ふとした瞬間、「自分の居場所はどこだろう?」と考える日々が続きました。
本当に救いになったのは、週末に通い始めた日本語補習校や地域の日本人会など、アメリカという広い社会の中で自然と生まれた「日本人コミュニティ」でした。
最初は母に連れられて補習校へ行き、校門前のにぎやかな日本語の会話に圧倒されましたが、同じ境遇の子どもたちが多く、互いに「うまく英語が話せない」「日本の給食が恋しい」といった話題で盛り上がり、すぐに打ち解けることができました。特に、休み時間や昼食時、みんなで集まって笑い合ったことが、大きな支えになったと今でも思います。

今振り返れば、そこは心の安全地帯であり、情報の宝庫であり、そして文化的なホームグラウンドでもありました!
日本人コミュニティとは?

アメリカの都市部には、多くの日本人が暮らしており、それぞれの地域で自然発生的にコミュニティが形成されています。
- 日本語補習校や土曜学校
- 日本人会、PTA、地域ボランティア団体
- LINEやFacebookの在米日本人グループ
- 日本人教会や文化センター
- 習いごと(ピアノ、水泳、習字など)
私は中学1年で渡米し、現地校に通いながら、毎週土曜日には日本語補習校に通っていました。
そこには、私と同じように英語に悪戦苦闘している子、日本語の読み書きを保つために通っている子、将来日本に帰国する予定の子など、いろいろな事情を持つ仲間がいました。
初めてのつながりは「補習校の門前」から

最初の友達は現地校ではなく、補習校でできました。
補習校に初めて通った日、教室前で緊張して待っていると、「どこから来たの?」と声をかけてくれた男の子がいました。
彼は私より先に渡米していた経験者で、教室の使い方やアメリカ生活のコツ、日本食スーパーの場所まで教えてくれました。ある土曜日には、学校帰りにみんなで近くのファストフード店に行き、お互いの現地校の話や、英語で迷った時のエピソードを披露し合って自然と仲間意識が芽生えました。
時には補習校メンバーでアメリカの映画館にチャレンジし、わからない英語だらけでもみんなで笑い飛ばしたのは今でも宝物の思い出です。

あの時間は、まさに週に一度の心のリセットでした。
日本人会に参加してみて分かったこと
週末の補習校だけでなく、地域の日本人会による季節イベントはとても貴重でした。
例えば、毎年8月に開かれる夏祭りでは、自分で選んだ浴衣を着て皆で屋台を手伝い、文化紹介の一役を担いました。当日は現地アメリカ人のお友達も一緒に参加し、金魚すくいや和式のゲームを英語で説明する場面も。
日本語が通じる安心感のなかで、自分流の英語でアクティビティを案内するという新しい挑戦ができたのです。また、高校生になると日本人会主催の運動会や料理教室にも積極的に参加するようになり、先輩の進路相談を受けたり、アメリカ生活の悩みを打ち明けたりできる関係が作れました。
高校生になってからは、日本人会主催のスポーツ大会に参加しました。バレーボールやドッジボールの試合では、年齢も職業もバラバラな人たちと同じチームになり、試合後には「将来はどうするの?」なんて大人に混じって話す機会もありました。
今思えば、そうした場が「日本語で安心して自己表現できる訓練の場」になっていたのだと思います。
距離感と関わり方:全員と仲良くする必要はない

日本人同士でも意外に性格や価値観の違いがあり、時にはグループの仲間との距離感に悩むこともありました。
特に中学時代は「全員と仲良くしなければ」と思いがちでしたが、だんだんと無理せず相性が合う友人と深く付き合い、必要以上に他人のペースに合わせるのはやめるようになりました。
たとえば、週末の遊びの誘いを断ることも気まずさを感じることはなくなり、自分らしい距離感でコミュニティと関われるようになったのは大きな成長ポイントでした。
高校生になると、無理に全員と親しくなる必要はないと割り切れるようになりました。
気が合う友達とは深く、そうでない人とは挨拶程度──このスタンスのおかげで、コミュニティが心地よい場所であり続けました。

どこに住んでいても人間関係の悩みはあるものですね
日本人以外の友達をつくるステップにも
日本人コミュニティの友人とは、たまにホームパーティーやピクニックを企画しました。ある日、友達の家で開催されたポットラックに、現地校のアメリカ人の友達も招待されたことで、思わぬ交流が生まれました。
最初は日本語と英語が入り交じる会話でしたが、徐々にそれぞれが自分の文化や趣味について語り合うように。
別の機会では、現地のクラブ活動や文化祭にも日本人仲間と一緒に参加し、アメリカ人の友人にも日本文化の魅力を伝えることができました。それがきっかけとなり、英語で積極的に話す自信につながりました。
また、日本文化紹介イベントで浴衣を着て英語で説明する役を任され、現地の人と自然に会話できたことは大きな自信になりました。
おわりに:心の居場所と広がりの起点に
振り返ると、アメリカでの中高生活の苦楽を支えてくれたのは、現地校と並行して出会えた日本人コミュニティの存在でした。
そこでは、悩みや喜びを共有できる仲間がいて、英語に自信がなくても素の自分でいられる場所があります。そうした人間関係が、異文化のなかでも安心感を得る支えや、グローバルな視点で成長する原点になりました。
今、同じような立場でアメリカ生活に挑戦している日本人の中高生には、「一人で頑張ろう」とするよりも、コミュニティの力を素直に頼りながら、自分らしい居場所を見つけて欲しいと心から伝えたいです。

だからこそ、これから渡米する人や、今アメリカで暮らしている中高生には、「現地校だけで頑張ろう」とせず、このもう一つの学校をぜひ活用してほしいと思います。
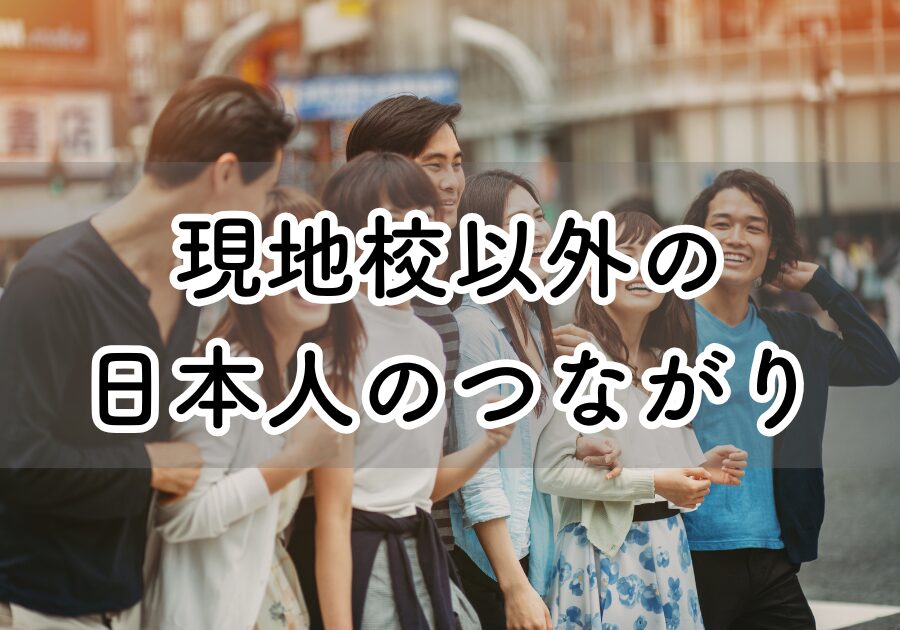
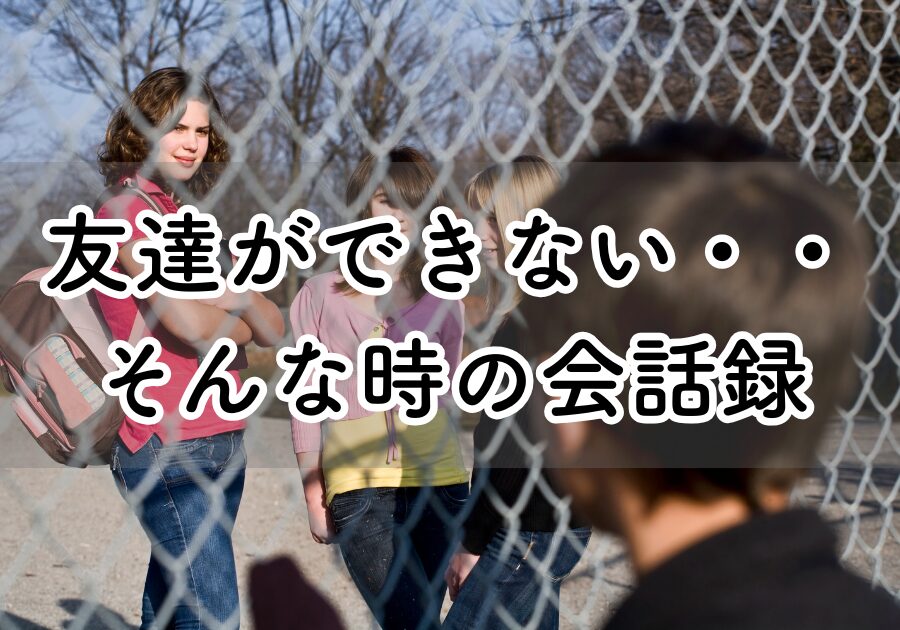
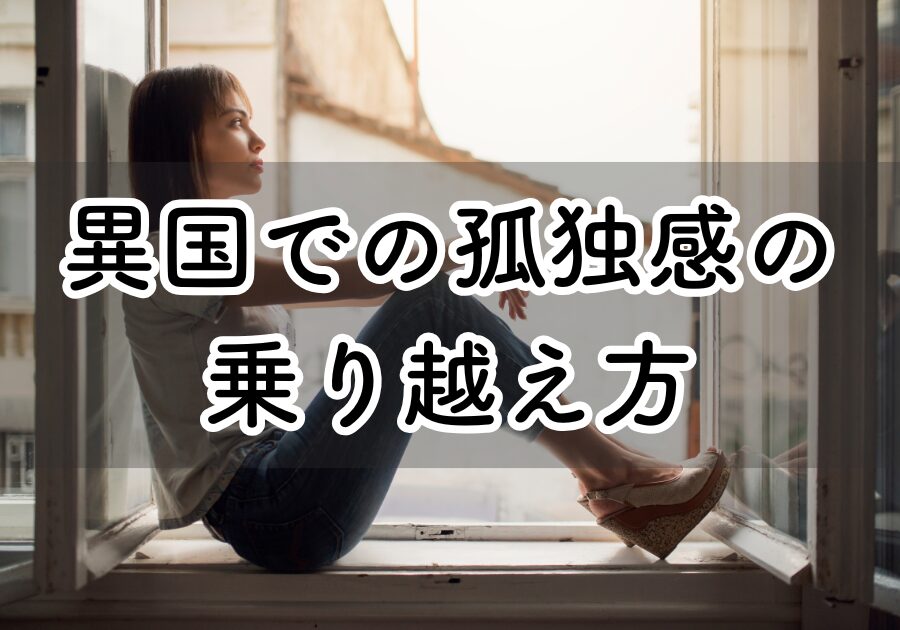
コメント